つわりで甘いものばかり…虫歯リスクが気になる妊婦さんのための対策ガイド
妊娠中に甘いものが欲しくなる理由と身体の変化

・つわりによる味覚の変化と甘味への欲求メカニズム
妊娠初期に多くの方が経験するつわりは、味覚や嗅覚に大きな変化をもたらします。普段好んでいた食べ物が急に受け付けなくなったり、逆に今まで苦手だった食べ物を欲するようになったりするのは、つわりの典型的な症状の一つです。
特に注目すべきは、酸味や苦味に対する感受性が高まることです。コーヒーの苦味や柑橘類の酸味が強く感じられるようになり、これらの刺激を避けるために、口当たりの優しい甘い食べ物を自然と求めるようになります。また、甘味は脳内でセロトニンの分泌を促し、つわりによる不快感や気分の落ち込みを和らげる効果があることも、甘いもの欲求の背景にあります。
妊娠中の味覚変化は、妊娠5~6週頃から始まり、多くの場合妊娠16週頃まで続きます。この期間中は、甘い食べ物が唯一口にできる食べ物となってしまうケースも珍しくありません。
・妊娠ホルモンが引き起こす食事の好みの変化
妊娠すると、女性の身体では劇的なホルモンバランスの変化が起こります。特にプロゲステロン(黄体ホルモン)とエストロゲン(卵胞ホルモン)の分泌量が大幅に増加し、これらのホルモンが味覚受容体や嗅覚受容体に直接影響を与えます。
プロゲステロンは消化器系の働きを緩やかにし、胃の動きを鈍らせる作用があります。このため、消化に時間のかかる脂っこいものや繊維質の多い食べ物よりも、消化吸収の早い糖質、特に単糖類を多く含む甘い食べ物を身体が求めるようになります。
また、エストロゲンの急激な増加は、脳の食欲中枢に影響を与え、特定の食べ物に対する強い欲求を生み出します。妊娠中に「○○が食べたくて仕方がない」という強い欲求が生まれるのは、このホルモンの働きによるものです。甘いものへの欲求もその一つで、チョコレートやアイスクリーム、果物などを無性に食べたくなる妊婦さんが多いのはこのためです。
これらのホルモン変化は妊娠期間中継続するため、甘いもの欲求も妊娠全期間を通じて続く可能性があります。
・エネルギー補給と血糖値維持のための身体の反応
妊娠中の身体は、母体と胎児の両方に必要なエネルギーを確保するため、通常時とは異なる代謝パターンを示します。妊娠中期以降、胎児の急速な成長に伴い、母体のエネルギー需要は妊娠前と比べて約300~500kcal増加します。
この増加したエネルギー需要を満たすため、身体は効率的にエネルギーを得られる糖質を優先的に求めるようになります。特に、即座にエネルギーに変換される単糖類(ブドウ糖、果糖など)を含む甘い食べ物への欲求が強くなるのは、身体の合理的な反応といえます。
また、妊娠中はインスリンの働きが変化し、血糖値が不安定になりやすい状態にあります。血糖値が急激に下がると、脳は即座にエネルギー源となる糖分の摂取を促すシグナルを送ります。これが「急に甘いものが食べたくなる」という現象として現れます。
さらに、妊娠中は基礎代謝が上がるため、安静時でも多くのエネルギーを消費します。このため、手軽にエネルギー補給できる甘い食べ物や飲み物を頻繁に欲するようになります。
妊娠後期になると、大きくなった子宮が胃を圧迫し、一度に多くの食事を摂ることが困難になります。このため、少量でも効率的にエネルギーを得られる甘い食べ物を、間食として頻繁に摂取したくなる傾向が強まります。
これらの生理的変化により、妊娠中の甘いもの欲求は自然な現象であり、適切にコントロールすれば母体と胎児の健康維持に役立ちます。しかし、過度な糖分摂取は虫歯リスクを高めるため、歯科医師と相談しながら適切な口腔ケアを継続することが重要です。
妊娠期の口腔環境が悪化する3つの要因
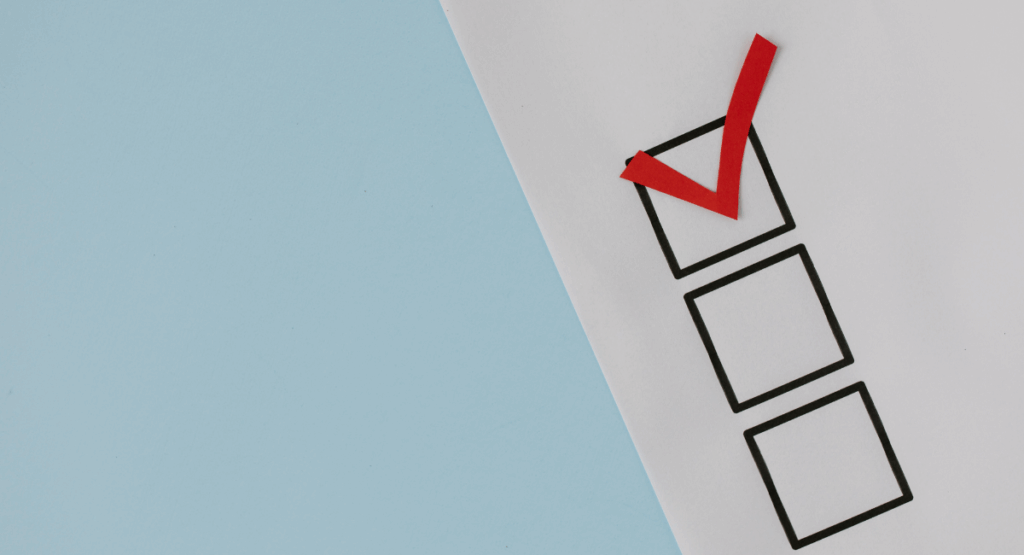
・妊娠性歯肉炎の発症メカニズムと症状
妊娠中のホルモンバランスの劇的な変化は、歯肉に大きな影響を与えます。特にプロゲステロンとエストロゲンの増加により、歯肉の血管透過性が高まり、炎症を引き起こしやすい状態になります。
妊娠性歯肉炎の主な特徴は以下のとおりです:
歯肉の腫脹と赤み
妊娠2~8か月頃に最も顕著となり、歯肉が通常よりも赤く、腫れぼったくなります。軽く触れただけでも出血しやすい状態になります。
歯肉の脆弱性
ホルモン変化により歯肉組織が柔らかくなり、細菌に対する抵抗力が低下します。これにより、軽微な刺激でも簡単に炎症を起こしやすくなります。
プラーク感受性の増加
妊娠中は歯垢(プラーク)に対する歯肉の反応が通常より敏感になり、少量のプラークでも激しい炎症反応を示すことがあります。
・唾液の質と量の変化による自浄作用の低下
唾液は口腔内の自然な防御システムとして重要な役割を果たしていますが、妊娠中はその機能が大きく変化します。
唾液の変化による主な影響:
●分泌量の減少
妊娠中のホルモン変化により、唾液の分泌量が約30%減少することがあります。唾液量の減少は、口腔内の自浄作用を著しく低下させます。
●pH値の変化
唾液のpH値が通常より酸性に傾きやすくなり、歯のエナメル質を脱灰しやすい環境を作り出します。これは虫歯リスクを significantly 高めます。
●ミネラル組成の変化
唾液に含まれるカルシウムやリン酸イオンの濃度が変化し、歯のリミネラリゼーション(再石灰化)能力が低下します。
・つわりによる歯磨き困難と口腔ケア不足の影響
つわりは妊娠中の口腔ケアを困難にする大きな要因の一つです。
つわりが口腔ケアに与える具体的な影響:
●歯磨き行動の阻害
吐き気や嘔吐反射により、歯ブラシを口に入れること自体が困難になります。結果として、歯磨きの頻度や質が大幅に低下します。
●口腔ケア用品への過敏反応
歯磨き粉の味やにおい、歯ブラシの感触に対して強い嫌悪感を感じ、口腔ケアを避けてしまうことがあります。
●口腔内細菌増殖のリスク
十分な歯磨きができないことで、歯垢や食物残渣が口腔内に残存し、細菌が爆発的に増殖する危険性が高まります。
・対策のポイント
これらの口腔環境の変化に対処するためには:
・柔らかめの歯ブラシの使用
・アルコールフリーの低刺激な洗口液の活用
・小さな歯ブラシヘッドの使用
・食後のうがいの徹底
・定期的な歯科検診
が推奨されます。
妊娠中の口腔ケアは、単に歯や歯肉の健康を守るだけでなく、母体と胎児の全体的な健康に大きく関わる重要な要素です。歯科専門家と相談しながら、個々の状況に合わせた適切なケア方法を見つけることが大切です。
妊娠中の甘いもの摂取が歯に忍び寄るリスクと真実

・糖分と虫歯菌の知られざる攻防
私たちの口腔内には、常に数千種類の細菌が生息しています。その中でも最も厄介なのが「ミュータンス菌」と呼ばれる虫歯菌。妊娠中は、このミュータンス菌の活動が通常よりも活発になります。
甘いものを摂取するたびに、これらの細菌は糖分を即座に栄養源として取り込みます。驚くべきことに、たった5分で細菌は酸を産生し始め、歯のエナメル質を溶かし始めるのです。妊娠中はこの過程がさらに加速し、通常の2倍以上のスピードで歯を侵食する可能性があります。
・妊娠が歯質に与える目に見えない変化
妊娠中の身体は、胎児の成長のためにカルシウムを優先的に使用します。その結果、母体の歯は徐々に脆弱化していきます。これは単なる栄養不足ではなく、ホルモンバランスの劇的な変化が引き起こす生理的な現象なのです。
エナメル質の再石灰化能力が低下し、一度できた虫歯はかつてないスピードで進行します。さらに、唾液の緩衝作用も低下するため、口腔内の酸性環境が長時間続きやすくなります。まさに、歯にとって最も脆弱な時期と言えるでしょう。
・歯周病が産む深刻なリスク
最も衝撃的なのは、妊娠中の歯周病が早産や低体重児出産のリスクを高める可能性があることです。口腔内の慢性炎症は、血流を通じて胎盤に炎症性サイトカインを送り込みます。
これらの炎症性物質は、子宮頸管の収縮を誘発し、早産のリスクを4〜7倍に引き上げる可能性があります。単なる歯の問題ではなく、胎児の健康直結する深刻な問題なのです。
・リスク軽減のための実践的アプローチ
では、どのように対処すればよいのでしょうか?完全に甘いものを避ける必要はありません。むしろ、賢く付き合うことが重要です。
1. 甘いものは一度に集中して摂取する
2. 食後は必ず水でうがい
3. フッ素入り歯磨き粉を使用
4. カルシウムとビタミンDを意識的に摂取
5. 定期的な歯科検診を怠らない
特に重要なのは、つわりなどで歯磨きが難しい時期も、口腔内を清潔に保つ工夫です。無理をせず、状況に応じた柔軟なアプローチが求められます。
妊娠中の口腔ケアは、単なる歯の健康管理を超えて、母体と胎児の未来を守る重要な取り組みなのです。甘いものへの欲求と向き合いながら、健康的で輝く妊娠生活を送りましょう。
妊娠中でも安全にできる虫歯予防の基本対策

・妊婦さんに適した歯磨きのタイミングと方法
妊娠中はホルモンバランスの変化やつわりなどの影響で、お口の中の環境が普段とは大きく異なります。そのため、歯磨きのタイミングや方法にも少し工夫が必要です。
【歯磨きのタイミング:体調を最優先に】
虫歯予防の基本は「食後なるべく早く」の歯磨きですが、つわりが辛い時期に無理をする必要はまったくありません。気分が悪くなってしまうと、歯磨き自体が苦痛になり、かえってケアから遠ざかってしまう原因にもなりかねます。
体調の良い時を見計らって:
「食後」にこだわらず、1日の中で少しでも体調が優れている時間帯に歯磨きを行いましょう。
「就寝前」だけは丁寧に:
1日1回、もし念入りに磨けるタイミングを選ぶなら「就寝前」が最も効果的です。眠っている間は唾液の分泌量が減り、虫歯菌が最も活発になる時間帯です。ここでしっかり汚れを落としておくことが、虫歯リスクを大きく下げてくれます。
難しい時はうがいだけでも:
どうしても歯ブラシを口に入れるのが辛い時は、水やお茶でぶくぶくうがいをするだけでも、食べかすを洗い流し、お口の中を中性に近づける効果が期待できます。
【歯磨きの方法:つわりを乗り切る工夫】
吐き気を催さずに磨くための、ちょっとしたコツをご紹介します。
歯ブラシは小さめを選ぶ:
ヘッド部分が小さい「コンパクトヘッド」の歯ブラシを選ぶと、奥歯まで入れても喉への刺激が少なくなります。
下を向いて磨く:
少し前屈みになり、顔を下に向けて磨くことで、唾液や泡が喉の奥へ流れ込むのを防ぎ、吐き気を感じにくくなります。
歯磨き粉を工夫する:
香味の強い歯磨き粉が刺激になる場合は、香りのマイルドなものや、発泡剤の少ないジェルタイプなどを試してみましょう。思い切って歯磨き粉をつけずに、水だけで「から磨き」をするのも一つの手です。歯磨きで最も大切なのは、歯ブラシの毛先で物理的に汚れを落とすことだからです。
磨き方で大切なのは、力を入れすぎず、歯と歯茎の境目を優しく小刻みに動かすことです。妊娠中は歯茎が腫れやすく、出血しやすい状態(妊娠性歯肉炎)になりがちですが、それを恐れて磨かないと、さらに症状は悪化してしまいます。優しく丁寧にケアすることを心がけてください。
・フッ素配合歯磨き粉の安全な使用方法
「フッ素は赤ちゃんに影響がないの?」というご質問をよくいただきます。結論から申し上げますと、歯磨き粉に含まれるフッ素は、用法・用量を守って使用する限り、お母さん自身にもお腹の赤ちゃんにも安全です。
歯の表面に直接作用するフッ素が、飲み込まずに吐き出すことで体内に吸収される量はごく微量であり、心配する必要はありません。むしろ、フッ素を有効に活用することは、妊娠中のデリケートなお口を守る上で非常に重要です。
【フッ素がもたらす3つの効果】
歯を強くする:
歯の表面のエナメル質を、酸に溶けにくい安定した構造(フルオロアパタイト)に変え、歯質を強化します。
再石灰化を促す:
ごく初期の虫歯であれば、唾液の力で歯が修復される「再石灰化」という働きがあります。フッ素は、この修復プロセスを力強くサポートします。
虫歯菌の働きを弱める:
虫歯菌が酸を作り出す働きを抑制し、お口の環境を虫歯になりにくく整えます。
【効果を最大化する使い方】
適量を守る:
歯ブラシの毛先に「5mm〜1cm」程度(グリーンピース大)が目安です。つけすぎても効果が高まるわけではありません。
うがいは1回だけ:
磨き終わった後のうがいは、少量の水(おちょこ1杯程度)で、5秒ほど軽く1回だけ行うのがおすすめです。お口の中にフッ素成分をできるだけ長く留まらせることが、効果を高める秘訣です。
・洗口液やデンタルフロスの効果的な活用法
歯ブラシだけでは届かない場所のケアには、補助的な清掃用具が大きな力を発揮します。
【洗口液(マウスウォッシュ)】
つわりで歯磨きができない時の「応急処置」として、また歯磨きの仕上げとして非常に役立ちます。製品によって効果は様々ですが、虫歯菌や歯周病菌を殺菌する成分が含まれているもの、炎症を抑える成分が含まれているものなどがあります。
選ぶ際は、アルコールを含まない「ノンアルコールタイプ」で、刺激の少ないものを選ばれると、妊娠中でも安心して使いやすいでしょう。ただし、洗口液はあくまで補助的なものです。汚れを物理的に除去する歯磨きやフロスの代わりにはならない、という点は覚えておいてください。
【デンタルフロス・歯間ブラシ】
実は、歯ブラシだけで落とせる歯の汚れは、全体の約60%と言われています。残りの40%は、歯と歯の間に潜んでいます。この歯間の汚れこそが、虫歯や歯周病の最大の温床となるのです。
特に、歯茎が腫れやすい妊娠中は、歯間に汚れが溜まることで歯肉炎が悪化しやすくなります。デンタルフロスや歯間ブラシでこの汚れを取り除くことは、虫歯予防はもちろん、歯肉炎の予防・改善にも直結します。
使い始めは歯茎から出血することがあり、驚かれるかもしれません。しかし、それはそこに炎症が起きているサインです。怖がらずに優しくケアを続けることで、2週間ほどで歯茎が引き締まり、出血は次第に収まってきます。もし痛みが続いたり、出血がひどい場合は、無理せず一度ご相談ください。
甘いものを食べる時の工夫とタイミング

・ダラダラ食べを避ける時間管理のコツ
虫歯予防において、何を食べるかと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「食べ方」、特に「時間」の管理です。そのキーワードが「ダラダラ食べ」の回避です。
【なぜ「ダラダラ食べ」が良くないの?】
私たちの口の中では、食事をするたびに、目に見えない攻防が繰り広げられています。
脱灰(だっかい):
食べ物(特に糖分)がお口に入ると、虫歯菌がそれをエサにして「酸」を作り出します。この酸によって歯の表面のミネラルが溶け出す現象を「脱灰」といいます。
再石灰化(さいせっかいか):
食後しばらくすると、唾液が持つ力(緩衝能)によってお口の中が中性に戻り、溶け出したミネラルが再び歯の表面に補給され、修復されます。これを「再石灰化」と呼びます。
健康な歯は、この「脱灰」と「再石灰化」のバランスが保たれている状態です。しかし、「ダラダラ食べ」をすると、お口の中が酸性になっている時間が長くなり、再石灰化による修復が追いつかなくなってしまいます。この脱灰に傾いた状態が続くことで、やがて歯に穴があき、虫歯へと進行してしまうのです。
【時間管理の具体的なコツ】
おやつの時間を決める:
「15時に食べる」など、間食の時間をしっかり決める習慣をつけましょう。時間を決めることで、お口の中が酸性になる時間を限定し、再石灰化の時間を十分に確保できます。
量を決めて、すぐに片付ける:
あらかじめ食べる量を小皿に取り分け、食べ終わったらすぐに袋や箱をしまいましょう。目の前にあると、つい手が伸びてしまうのを防ぐ効果があります。
甘い飲み物にも注意:
ジュースやスポーツドリンク、加糖のコーヒーなどを、仕事や家事をしながら少しずつ飲むのも「ダラダラ食べ」と同じです。甘い飲み物は食事やおやつの時間と一緒に摂るようにし、普段の水分補給は水やお茶を選ぶように心がけましょう。
つわりなどで一度にたくさん食べられない時期は、「ちょこちょこ食べ」になることもあるかと思います。その場合も、時間を意識し、次に紹介するような虫歯になりにくい食品を選ぶなどの工夫を取り入れてみてください。
・虫歯になりにくい甘味料の選び方
「甘いもの=虫歯になる」と一括りに考える必要はありません。実は、甘さを感じる成分の中にも、虫歯菌が利用できない、あるいは虫歯予防に役立つものがあります。それが「代用甘味料」です。
お菓子やガムなどを選ぶ際に、パッケージの裏にある原材料表示を少しだけ気にして見てみてください。
キシリトール:
代用甘味料の代表格です。キシリトールの素晴らしい点は、虫歯菌が酸を作り出す原料にできないだけでなく、虫歯菌そのものの活動を弱める効果も報告されていることです。食後にキシリトール100%のガムやタブレットを摂ることは、非常に効果的な虫歯予防法として知られています。
エリスリトール、マルチトールなど(糖アルコール類):
キシリトールと同じ糖アルコールの一種で、これらも虫歯菌が酸を作る原因になりにくい甘味料です。
これらの代用甘味料を使用した「シュガーレス」「糖類ゼロ」と表示されたお菓子は、一般的な砂糖を使ったお菓子に比べて虫歯になるリスクを大幅に低減できます。甘いものが食べたくなった時には、こうした製品を賢く選ぶのがおすすめです。
ただし、「カロリーゼロ」だからといって必ずしも虫歯にならないわけではありません。商品によっては虫歯の原因となる糖質が含まれている場合もあるため、やはり原材料表示で「キシリトール」などの表記を確認する習慣をつけると、より安心です。
・食後の口腔ケアで酸性化を防ぐ方法
甘いものを楽しんだ後は、できるだけ速やかにお口の中を酸性から中性の状態へ戻してあげることが、歯を守るための最後の砦となります。
もちろん、食後すぐに歯磨きができるのが理想ですが、外出先やつわりで体調が優れない時など、そうはいかない場面も多いでしょう。そんな時に役立つ、手軽なケア方法をご紹介します。
食後すぐの「ぶくぶくうがい」:
最も簡単で、かつ効果的な方法です。水やお茶で口をゆすぐだけで、お口の中に残った食べかすや糖分を洗い流し、酸性の状態を和らげることができます。食後や間食後、これを習慣にするだけでも大きな違いが生まれます。
キシリトールガムを噛む:
前述の通り、キシリトール自体に虫歯予防効果があるのに加え、「ガムを噛む」という行為が唾液の分泌を活発にします。唾液は天然の洗浄剤であり、酸を中和する働きを持っています。食後に5分ほど噛むだけで、お口の環境を素早く改善する手助けとなります。
デンタルリンス(洗口液)の活用:
ノンアルコールで刺激の少ない洗口液も、歯磨きができない時の心強い味方です。お口をすすぐことで、さっぱりするだけでなく、製品によっては殺菌成分が虫歯菌の活動を抑えてくれます。
これらの方法は、あくまで歯磨きができない時の応急処置です。1日の中のどこか体調の良いタイミング、特に菌の活動が活発になる「就寝前」には、フロスや歯ブラシを使った丁寧なセルフケアで、一日の汚れをリセットすることを忘れないようにしましょう。
つわり中でもできる口腔ケアの実践テクニック

・吐き気を抑えながら歯磨きをする方法
歯磨き中の「おえっ」となる感覚(嘔吐反射)は、誰にでも起こりうることですが、つわり中は特に敏感になりがちです。この不快感を少しでも和らげるための、いくつかのコツがあります。
●姿勢を工夫する:「下を向いて」磨く
洗面台に向かう時、鏡を見ながらまっすぐ立つのではなく、少し前屈みになって「顔を下に向けて」磨いてみてください。こうすることで、口の中に溜まった唾液や歯磨き粉の泡が、喉の奥へ流れ込むのを物理的に防ぐことができます。吐き気の原因となる喉への刺激を、これだけで大きく軽減できます。
●意識をそらす:「ながら磨き」
「今から歯を磨くぞ」と意気込むと、かえって吐き気に意識が集中してしまいがちです。テレビや動画を見ながら、あるいは好きな音楽を聴きながら、何気なく手を動かす「ながら磨き」を試してみるのも良い方法です。歯磨きという行為から意識をそらすことで、リラックスして行えることがあります。
●呼吸を整える:鼻でゆっくり呼吸する
歯ブラシを口に入れている間、息を止めたり、口で呼吸したりすると吐き気を催しやすくなります。意識して「鼻からゆっくり息を吸い、鼻から吐く」ことを心がけてみましょう。深い呼吸はリラックス効果もあり、嘔吐反射を抑えるのに役立ちます。
●歯磨き粉を見直す
香りの強いミント系や、泡立ちの良い歯磨き粉が刺激になっているケースは非常に多いです。香りのないもの、あるいはマイルドな香味のもの、泡立ちの少ないジェルタイプのものなどに変えてみるだけで、驚くほど楽になることがあります。思い切って歯磨き粉をつけずに、水だけで磨く「から磨き」でも、歯の表面の汚れ(プラーク)を落とす効果は十分にあります。
・小さなヘッドの歯ブラシや電動歯ブラシの活用
使う道具を少し変えるだけで、歯磨きのハードルはぐっと下がります。
●ヘッドの小さな歯ブラシを選ぶ
歯ブラシのヘッド(ブラシ部分)が大きいと、奥歯を磨く際に頬の内側や舌の奥を刺激し、吐き気のトリガーになりやすいです。普段お使いのものより、ヘッドが一回りも二回りも小さい「コンパクトヘッド」や「超コンパクトヘッド」を選んでみてください。ドラッグストアなどで販売されている、小学生向けの「子ども用歯ブラシ」を使ってみるのも、実は非常に有効な方法です。
●「タフトブラシ」をプラスする
「タフトブラシ」とは、毛束が一つだけの、鉛筆の先のような形をした小さな歯ブラシです。奥歯の奥や、歯が重なって生えている場所など、通常の歯ブラシでは届きにくい場所をピンポイントで磨くことができます。気持ち悪さを感じやすい奥歯だけ、このタフトブラシでサッと磨くだけでも、虫歯リスクの高い場所のケアができます。
●電動歯ブラシを試してみる
電動歯ブラシは、短時間で効率よく汚れを落とせるのが大きなメリットです。自分でゴシゴシと手を動かす必要がなく、歯に軽く当てるだけで済むため、喉への刺激を最小限に抑えながらケアができます。つわりで辛い時間を少しでも短縮したい、という方には有効な選択肢の一つです。ただし、振動が苦手な方もいらっしゃるので、もし試せる機会があれば、ご自身に合うかどうか確認してみるのが良いでしょう。
・うがいや口をすすぐことから始める段階的ケア
「どうしても歯ブラシを口に入れること自体が無理…」そんな日があって当然です。そんな時は、無理に歯を磨こうとせず、まずは「お口をすすぐ」ことから始めてみましょう。それだけでも、立派な口腔ケアです。
【ステップ1:まずは、うがいだけでもOK】
食後や甘いものを口にした後、水やお茶でぶくぶくと口をゆすぐだけでも、お口の中に残った食べかすを洗い流し、虫歯菌が作り出した酸を中和する助けになります。これだけでも、やらないのとは大違い。まずはこれを目標にしてみましょう。
【ステップ2:洗口液(マウスウォッシュ)を使ってみる】
うがいに慣れてきたら、ノンアルコールで低刺激タイプの洗口液を試してみるのも良いでしょう。気分がさっぱりするだけでなく、製品によっては虫歯菌の活動を抑える効果も期待できます。
【ステップ3:できる時に、できる場所だけ磨く】
少し体調の良いタイミングがあれば、まずは前歯だけ、あるいは吐き気を感じにくい下の歯だけ磨いてみる。あるいは、前述のタフトブラシで一番気になる奥歯を1本だけ磨いてみる。そんな「部分磨き」から再開してみましょう。
大切なのは、「100点か0点か」で考えないことです。つわり中の20点のケアは、何もしない0点よりも、はるかに価値があります。ご自身の体調を第一に、焦らず、あなたのペースでケアを続けていくことが、お母さんとお腹の赤ちゃんの健康を守ることに繋がります。
妊娠期別の歯科受診のベストタイミング

・妊娠初期・中期・後期それぞれの治療可能範囲
妊娠期間中、お母さんの体調や胎児の発育状況は刻々と変化します。歯科治療も、その変化に細やかに合わせて行う必要があります。
妊娠初期(〜15週頃まで)
この時期は、赤ちゃんの脳や心臓といった大切な器官が作られる、非常にデリケートな期間です。また、多くの妊婦さんがつわりに悩まされる時期でもあります。そのため、原則として歯科治療は応急処置に留めるのが一般的です。「歯が痛む」「歯茎が腫れた」といった緊急のトラブルに対して、痛みを和らげる処置を中心に行います。
抜歯や神経の治療といった本格的な治療は、安定期に入ってから行う方が望ましいでしょう。
ただし、歯科健診やカウンセリング、ご自宅でのケア方法についてのアドバイスを受けることは全く問題ありません。むしろ、つわりで歯磨きが難しいこの時期にこそ、専門家のアドバイスが役立ちます。
妊娠中期(16週〜27週頃まで)
いわゆる「安定期」と呼ばれるこの時期が、歯科治療を受けるのに最も適したベストタイミングです。つわりが落ち着き、お母さんの体調も安定してくるため、心身ともにゆとりを持って治療に臨むことができます。
虫歯の治療や歯周病のケア、親知らずの抜歯など、ほとんどの一般的な歯科治療を安全に行うことが可能です。もしお口の中に気になる点があれば、ぜひこの時期を逃さずに受診されることをお勧めします。
妊娠後期(28週頃〜出産まで)
出産が近づき、お腹が大きくなってくると、診療台で長時間仰向けの姿勢を保つことが身体的な負担になることがあります(仰臥位低血圧症候群※)。また、早産のリスクなども考慮し、この時期の歯科治療も基本的には応急処置が中心となります。
もし治療が必要な場合も、できるだけ短時間で済むように、また、楽な体勢を保てるように最大限配慮します。出産後の育児はとても忙しくなりますので、この時期に一度健診を受け、産後に治療が必要になりそうな箇所がないかチェックしておくだけでも安心です。
※仰臥位低血圧症候群:仰向けになることで、大きくなった子宮が下大静脈という太い血管を圧迫し、血圧が低下して気分が悪くなる状態のこと。
・安定期に行うべき予防処置と治療内容
歯科治療のベストタイミングである安定期。この貴重な時期を有効に活用して、お口のトラブルを未然に防ぎ、必要な治療を済ませておきましょう。出産後は、ご自身の歯の治療のために時間を確保するのが難しくなることが多いため、まさに「今」がチャンスです。
【推奨される予防処置】
歯科健診:
まずは専門家の目で、虫歯や歯周病のリスクがないかをくまなくチェックします。
歯のクリーニング(PMTC):
毎日の歯磨きでは落としきれない歯石や、細菌のすみかとなるバイオフィルム(ぬめり)を、専門の機械を使って徹底的に除去します。妊娠中はホルモンの影響で歯茎が腫れやすいため(妊娠性歯肉炎)、このクリーニングは歯周病の予防・改善に非常に効果的です。
フッ素塗布:
歯の質を強くし、虫歯菌が出す酸への抵抗力を高めます。妊娠中に高まる虫歯リスクから、ご自身の歯を守るための有効な手段です。
セルフケア指導:
現在のお口の状態やライフスタイルに合わせた、最適な歯磨きの方法や補助清掃用具(フロスなど)の使い方を改めて確認します。
【この時期に行える治療】
安定期であれば、ほとんどの一般的な歯科治療が可能です。小さな虫歯を放置すると、産後に痛みだすなど大きなトラブルに発展しかねません。この時期にきちんと治療しておくことで、安心して出産・育児に臨むことができます。
また、妊娠中に悪化しやすい歯周病の治療も重要です。重度の歯周病は、早産や低体重児出産のリスクを高める可能性も指摘されています。お母さんと赤ちゃんの両方の健康のために、適切な治療を受けることが推奨されます。
・緊急時の歯科治療における安全性の確保
「妊娠中だけど、急に歯が激しく痛み出した…」
そんな時、決して我慢しないでください。痛みを我慢する強いストレスや、歯の根の先に溜まった膿などによる感染は、お母さんとお腹の赤ちゃんにとって、適切な歯科治療を受けること以上に悪影響を及ぼす可能性があります。
緊急時であっても、私たちは母子の安全を最優先に考え、最大限の配慮をもって治療にあたります。
産婦人科医との連携:
歯科医院を受診される際は、必ず妊娠中であること、現在の週数、そしてかかりつけの産婦人科をお伝えください。必要に応じて、当院から産婦人科の先生に連絡を取り、情報を共有しながら、最も安全な治療法を選択します。
レントゲン撮影について:
歯科で使用するレントゲンの放射線量はごくわずかで、撮影部位もお口周りに限定されます。さらに、撮影の際は必ず放射線を遮蔽する防護用のエプロンを着用しますので、お腹の赤ちゃんへの影響はまず心配ありません。診断のためにどうしても必要な場合に限り、最小限の枚数で撮影を行います。
●麻酔について:
歯科治療で用いる局所麻酔は、通常の使用量であればお腹の赤ちゃんへの影響はほとんどないと考えられています。麻酔なしで痛みを我慢しながら治療を受けるストレスの方が、母体にとってはずっと大きな負担となります。
●お薬(投薬)について:
痛み止めや抗生物質が必要な場合も、産婦人科で処方されるものと同様に、妊娠中でも比較的安全性の高いお薬を選択して処方します。自己判断で市販薬を服用することは絶対に避けてください。
栄養バランスを考えた歯に優しい食事選択

・カルシウムやビタミンDを含む食材の積極的摂取
歯や骨の主成分である「カルシウム」が大切なことは、多くの方がご存知かと思います。そして、そのカルシウムの吸収を助け、効率よく体内に取り込むために不可欠なパートナーが「ビタミンD」です。この二つは、ぜひセットで摂取することを意識していただきたい栄養素です。
「妊娠すると、お腹の赤ちゃんにカルシウムを奪われて歯がもろくなる」という話を耳にしたことがあるかもしれませんが、これは正確には正しくありません。お腹の赤ちゃんに必要なカルシウムは、お母さんが食事から摂ったものが優先的に供給されます。歯から直接カルシウムが溶け出すわけではないのです。妊娠中に歯のトラブルが増えるのは、ホルモンバランスの変化やつわりによるケア不足が主な原因と考えられています。
ですから、過度に心配する必要はありません。むしろ、お母さん自身の健康と、これから作られる赤ちゃんの丈夫な歯と骨のために、これらの栄養素を積極的に食事に取り入れることが大切です。
【カルシウムが豊富な食材】
・牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品
・豆腐、納豆、厚揚げなどの大豆製品
・しらす干し、桜えびなどの小魚
・小松菜、水菜などの緑黄色野菜
・ひじきなどの海藻類
【ビタミンDが豊富な食材】
・鮭、さんま、いわしなどの魚類
・きのこ類(特に、天日干しした干ししいたけはビタミンDが豊富です)
・卵
いつものお味噌汁に豆腐ときのこを加えたり、サラダにしらす干しをトッピングしたり。そんな小さな工夫で、カルシウムとビタミンDを一緒に摂ることができます。
・咀嚼を促す食材で唾液分泌を増やす工夫
私たちの口の中には、「唾液」という非常に優秀な“お口の万能薬”が存在します。唾液には、食べかすを洗い流す「洗浄作用」、食後の酸性に傾いたお口の中を中和する「緩衝作用」、初期虫歯を修復する「再石灰化作用」など、歯を守るための様々な働きがあります。
この唾液の分泌を促す最も簡単で効果的な方法が、「よく噛むこと(咀嚼)」です。噛む回数が増えれば増えるほど、唾液はたくさん分泌されます。
そこで意識したいのが、「噛みごたえのある食材」を食事に取り入れることです。
【噛みごたえのある食材の例】
・ごぼう、れんこん、にんじんなどの根菜類
・きのこ類、わかめなどの海藻類
・玄米や雑穀米
・ナッツ類やごま
これらの食材を、普段の食事に少しプラスしてみましょう。例えば、白米を玄米に混ぜてみる、きんぴらごぼうを常備菜にする、といった工夫がおすすめです。また、調理の際に野菜を少し大きめにカットするだけでも、自然と噛む回数を増やすことができます。
「一口30回」を目標によく噛んで食べる習慣は、唾液の分泌を促すだけでなく、満腹感を得やすくして食べ過ぎを防いだり、消化を助けたりと、体にとっても多くのメリットがあります。
・妊娠中に避けるべき食品と推奨される代替食品
歯の健康という観点から見た場合、特に注意したいのは「糖分が多く、お口の中に長く留まるもの」や「歯に付きやすいもの」、そして「酸性の強いもの」です。
【注意したい食品の例】
糖分が多く、停滞しやすいもの: キャラメル、ソフトキャンディー、あめ、ガムシロップ入りのジュースなど。これらは糖分が歯に長時間まとわりつき、お口の中が酸性になる時間が長くなってしまいます。
歯に付着しやすいもの: クッキー、ポテトチップスなどのスナック菓子、菓子パンなど。歯の溝や歯と歯の間に残りやすく、虫歯の原因となります。
酸性度の高いもの: 炭酸飲料、スポーツドリンク、栄養ドリンク、柑橘系の果物、酢の物など。これらは虫歯菌が作り出す酸とは別に、食品そのものの酸が歯を溶かす「酸蝕症(さんしょくしょう)」の原因になることがあります。つわり中に口をさっぱりさせたくて、こうしたものを頻繁に口にする場合は注意が必要です。
これらの食品を完全に断つ必要はありません。食べる時間を決め、ダラダラと食べ続けないこと。そして、食べた後には水で口をゆすぐ、といった工夫が大切です。
【間食におすすめの代替食品】
もし間食をするのであれば、お口の健康にも配慮した賢い選択を心がけましょう。
甘いものが欲しい時: 砂糖の代わりにキシリトールなどを使用したシュガーレスのガムやタブレット、果物(食べた後はうがいを)、食物繊維も豊富な焼き芋やふかし芋など。
小腹が空いた時: カルシウム補給にもなるチーズや無糖ヨーグルト、噛みごたえのあるナッツ類や小魚アーモンドなど。
産後に向けた長期的な口腔健康管理計画

・授乳期の口腔環境変化への備えと対策
出産という大仕事を終えたお母さんの体は、休む間もなく24時間体制の育児へと突入します。特に授乳期は、これまでの生活とは一変し、お口の環境も大きく変化しやすい時期です。
不規則な生活リズム: 頻繁な授乳や夜泣き対応による睡眠不足、自分の食事は後回しになりがちで、空腹を満たすための「ちょこちょこ食べ」が増える傾向にあります。これは、お口の中が酸性になる時間が長くなることを意味し、虫歯リスクを高める一因です。
●ケア時間の不足: 赤ちゃんのお世話に追われ、自分の歯をゆっくり磨く時間を確保するのが難しくなります。「歯磨きを忘れて寝てしまった」という経験は、多くの先輩ママが通る道です。
●唾液の質の変化: 産後のホルモンバランスの変化やストレス、睡眠不足などから、唾液の分泌量が減少したり、質が変化したりすることがあります。歯を守る力が弱まり、虫歯や歯周病が進行しやすくなります。
こうした変化に備え、完璧を目指すのではなく「賢く手を抜く」時短ケアを取り入れることが、産後の口腔ケアを続けるコツです。
●うがいを習慣に: 食事や授乳の後、すぐに歯が磨けなくても、水やお茶で口をゆすぐだけでも効果があります。洗面所にコップを常備しておきましょう。
●キシリトールを活用: 授乳中や赤ちゃんを抱っこしている時でも、キシリトール100%のガムやタブレットなら手軽に口にできます。唾液の分泌を促し、虫歯菌の活動を抑える助けになります。
●「産後歯科健診」のススメ: 多くの自治体では、妊婦歯科健診だけでなく、産後の歯科健診にも力を入れています。出産で変化したお口の状態を一度専門家にチェックしてもらい、プロのクリーニングを受けることで、その後のセルフケアが格段に楽になります。育児が少し落ち着いたタイミングで、ぜひ受診を計画してみてください。
・赤ちゃんの虫歯菌感染予防のための母親のケア
あまり知られていませんが、生まれたばかりの赤ちゃんのお口の中には、虫歯の原因となるミュータンス菌は一匹もいません。 では、どこからやってくるのか。その主な感染源は、残念ながら、最も身近にいるお母さんやお父さんなど、家族の唾液を介してであることが分かっています。
スプーンや箸の共有、熱い食べ物をフーフーして冷ましてあげる、愛情表現のキスなど、ごく日常的な行為の中で、唾液に含まれる虫歯菌が赤ちゃんの口へと移ってしまうのです。これを「母子感染(垂直感染)」と呼びます。
「キスもダメなの?」と心配になるかもしれませんが、神経質になりすぎる必要はありません。感染を100%防ぐことは現実的ではありませんし、スキンシップは親子の愛着形成に不可欠です。
ここで最も重要なのは、「感染の時期をできるだけ遅らせること」、そして「赤ちゃんにうつしてしまう虫歯菌の量を、そもそも少なくしておくこと」です。
そのために、お母さんにできる最も効果的で愛情深いプレゼントが、ご自身の口腔ケアを徹底し、お口の中の虫歯菌を減らしておくことなのです。
妊娠中から安定期を利用して虫歯治療を済ませ、歯科医院での専門的なクリーニングを定期的に受けること。そして、キシリトールを継続的に摂取することは、お母さん自身の口腔内の虫歯菌を減少させ、結果としてお子さんへの感染リスクを低減させることが多くの研究で報告されています。
・家族全体の口腔健康向上を目指した生活習慣
赤ちゃんの虫歯予防は、お母さん一人が背負うべき課題ではありません。お父さん(パートナー)をはじめ、同居するご家族全員で取り組むべき「家族の健康プロジェクト」です。
お父さんのお口に虫歯があれば、それが感染源になる可能性も十分にあります。ぜひ、ご夫婦で一緒に歯科健診を受け、お互いのお口の健康状態を確認し合う機会を持ってみてはいかがでしょうか。
【家族で始める新しいルール】
●甘いおやつは時間を決め、家族団らんの時間に一緒に楽しむ。
●食事の後の歯磨きを、家族みんなの習慣にする。
●普段の水分補給は、ジュースではなく水やお茶を基本にする。
●食器の共有や噛み与えは避ける意識を、家族全員で共有する。
こうした小さな習慣の積み重ねが、お子さんを虫歯から守るだけでなく、家族全員の健康意識を高めることに繋がります。
よくある質問Q&A

・Q1. 妊娠中の歯科治療は本当に安全なのでしょうか?
A. はい、適切な時期を選び、適切な配慮のもとで行う歯科治療は安全です。 むしろ、痛みを我慢したり、感染を放置したりする方が、お母さんとお腹の赤ちゃんにとって大きなストレスやリスクとなる場合があります。
最も治療に適しているのは、体調が安定する妊娠中期(安定期:16週〜27週頃)です。この時期であれば、虫歯治療や歯のクリーニングなど、ほとんどの一般的な歯科治療を安心して受けていただけます。
治療の際に用いる局所麻酔は、通常量では母子への影響はほとんどなく、痛みをなくすことで治療中のストレスを大幅に軽減できます。また、診断に必要なレントゲン撮影も、放射線量が極めて少ない歯科用のものであり、防護エプロンを着用するため、お腹の赤ちゃんへの影響はまず心配ありません。お薬が必要な場合も、産婦人科医と連携し、妊娠中でも安全性の高いものを選択します。
大切なのは、「妊娠中だから」と自己判断で受診を諦めないことです。必ず妊娠していることと週数をお伝えいただいた上で、まずはお気軽にご相談ください。
・Q2. つわりがひどくて歯磨きができない時はどうすれば良いですか?
A. まず、ご自身を責めないでください。つわりで歯磨きが辛いのは、多くの妊婦さんが経験することです。完璧を目指さず、その日の体調に合わせて「できること」を一つでも見つけることが大切です。
ステップ1:まずは「うがい」から
歯ブラシを口に入れるのが無理な日は、食後に水やお茶でぶくぶくうがいをするだけでも、お口の環境は大きく改善します。
ステップ2:「ながらケア」を取り入れる
体調が良い時間帯に、テレビを見ながらなど、リラックスした状態で歯磨きに挑戦してみましょう。ヘッドの小さな歯ブラシ(子ども用でも可)や、香りの少ない歯磨き粉、あるいは歯磨き粉なしの「から磨き」も有効です。下を向いて磨くと、唾液が喉に流れにくく、吐き気を抑えられます。
ステップ3:デンタルグッズに頼る
キシリトール配合のガムやタブレット、ノンアルコールの洗口液(マウスウォッシュ)なども、歯磨きができない時の心強い味方です。
「100点満点のケア」ではなく、「今日は20点できた」とご自身を認め、できる範囲でケアを続けることが、この時期を乗り切るための何よりの秘訣です。
・Q3. 甘いものを完全にやめることはできませんが、虫歯を防ぐ方法はありますか?
A. もちろんです。妊娠中に甘いものが欲しくなるのは自然なこと。我慢しすぎてストレスを溜めるよりも、「食べ方の工夫」で賢く付き合うことが、心と体の健康のために重要です。
ポイントは以下の3つです。
時間を決めて食べる: 最も避けたいのは「ダラダラ食べ」です。お口の中が酸性になる時間を短くするため、おやつは「15時に」などと時間を決め、短時間で楽しみましょう。
虫歯になりにくいものを選ぶ: 砂糖の代わりにキシリトールなどの代用甘味料が使われた「シュガーレス」のお菓子やガムを選ぶのがおすすめです。
食べた後のケアを徹底する: 食べた後はすぐに歯磨きをするのが理想ですが、難しければ水で口をゆすぐだけでも効果があります。食後のキシリトールガムも、唾液の分泌を促し、お口の中を中性に戻す手助けになります。
「完全に断つ」のではなく「上手にコントロールする」。
この意識を持つだけで、虫歯のリスクはぐっと減らすことができます。
・Q4. 妊娠中に歯茎から血が出るようになりましたが、大丈夫でしょうか?
A. 歯茎からの出血は、「妊娠性歯肉炎」のサインである可能性が高いです。これは、妊娠中に増加する女性ホルモンの影響で、特定の歯周病菌が活発になり、歯茎が腫れやすく、わずかな刺激でも出血しやすくなるために起こります。多くの妊婦さんが経験する症状であり、過度に心配する必要はありません。
しかし、「大丈夫」と放置して良いわけではありません。 出血を怖がって歯磨きを避けてしまうと、汚れ(プラーク)がさらに溜まり、症状は悪化してしまいます。柔らかめの歯ブラシを使い、歯と歯茎の境目を優しく、しかし丁寧に磨くことが改善への第一歩です。
この妊娠性歯肉炎を放置すると、本格的な歯周病へと進行するリスクもあります。歯周病は、早産や低体重児出産との関連も指摘されています。気になる出血が続くようでしたら、ぜひ一度、専門家によるチェックとクリーニングを受けることを強くお勧めします。
・Q5. 産まれてくる赤ちゃんに虫歯菌をうつさないためには何をすべきですか?
A. 生まれたばかりの赤ちゃんのお口には、虫歯菌はいません。主に家族の唾液を介して感染します(母子感染)。この感染のリスクをゼロにすることは困難ですが、お母さん(とご家族)ができる最も効果的な対策は、「ご自身のお口の中の虫歯菌を減らしておくこと」です。
具体的には、以下の3点が重要です。
妊娠中に歯科治療を済ませる: 安定期を利用して虫歯や歯周病の治療を完了させ、お口を健康な状態にしておきましょう。
専門的なクリーニングを受ける: 定期的に歯科医院で歯石やバイオフィルムを除去してもらうことで、セルフケアでは落としきれない細菌の巣をリセットできます。
キシリトールを習慣にする: キシリトールの継続的な摂取は、お口の中の虫歯菌の数を減らす効果が報告されており、お子さんへの感染リスクを低減するのに有効です。
スプーンの共有などを避けることも大切ですが、それ以上に、お母さん自身が清潔で健康なお口でいることが、お子さんへの最高のプレゼントになります。これは「マイナス1歳からの虫歯予防」の第一歩です。ご家族全員で、お口の健康に取り組んでいきましょう。
監修:愛育クリニック麻布歯科ユニット
所在地〒:東京都港区南麻布5丁目6-8 総合母子保健センター愛育クリニック
電話番号☎:03-3473-8243
*監修者
愛育クリニック麻布歯科ユニット
ドクター 安達 英一
*出身大学
日本大学歯学部
*経歴
・日本大学歯学部付属歯科病院 勤務
・東京都式根島歯科診療所 勤務
・長崎県澤本歯科医院 勤務
・医療法人社団東杏会丸ビル歯科 勤務
・愛育クリニック麻布歯科ユニット 開設
・愛育幼稚園 校医
・愛育養護学校 校医
・青山一丁目麻布歯科 開設
・区立西麻布保育園 園医
*所属
・日本歯科医師会
・東京都歯科医師会
・東京都港区麻布赤坂歯科医師会
・日本歯周病学会
・日本小児歯科学会
・日本歯科審美学会
・日本口腔インプラント学会

