妊娠中の歯医者、赤ちゃんへの影響は?産後とどっちが良いかママの疑問に答えます
1.妊娠がわかったらまず知りたいお口の変化

妊娠ホルモンが引き起こす歯ぐきの腫れと出血
エストロゲンやプロゲステロンが急増すると歯ぐきの血管が拡張し、わずかなプラークでも炎症が起こりやすくなります。これが「妊娠性歯肉炎」です。妊娠 2〜3 か月ごろから発症しやすく、赤み・腫れ・ブラッシング時の出血が主症状です。ホルモンの影響でコラーゲン線維がゆるむうえ免疫反応も変化し、防御力が低下するため細菌が侵入しやすい環境が生まれます。放置すると歯石が付き慢性化しやすく、出産後まで炎症が残るケースもあります。早期に歯科でのチェックとプロフェッショナルクリーニングを受け、妊娠期特有の歯肉炎を長引かせないことが母体と赤ちゃん双方の健康につながります。
つわりによる食習慣の変化と虫歯リスクの高まり
吐き気を避けるために酸味の強い飲料や糖質の高い間食が増えると、口腔内は酸性環境に傾き脱灰が進みます。さらに嘔吐で胃酸が逆流するとエナメル質が溶けやすくなるうえ、ブラッシング動作自体がつらい日もあり、プラーク滞留時間が延びて虫歯リスクが跳ね上がります。味や匂いの刺激で歯磨き粉が使えない場合は、小さめヘッドの歯ブラシと無香料ジェルを選び、うがいだけでも頻繁に行うことが重要です。食後すぐに磨けないときはキシリトールガムやフッ化物洗口を利用し、酸を中和させる工夫でエナメル質を守りましょう。
妊娠初期でもできる安全なセルフケアと歯科受診の目安
妊娠初期は流産リスクを懸念して受診をためらう方が多いものの、基本的な検診とクリーニングは母体にも胎児にも安全と国内外ガイドラインで示されています。体調が安定している時間帯を選び、診療チェアの角度を浅くしてもらえば負担を最小限に抑えられます。セルフケアでは、①フッ素配合歯磨き剤で 1 日 2 回以上丁寧にブラッシング、②出血部位はやさしくマッサージし血行を促進、③就寝前のデンタルフロスで歯間部の炎症を減らす、という三つの柱を徹底しましょう。早期から歯科医に相談して個別リスクを把握し、安定期に入るまでのケア計画を立てておくことが、後々の治療を最小限に抑える鍵となります。
2.“マタニティ歯科”が推奨される3つの医学的理由

早産・低体重児出産と歯周病の関連性
妊娠中の歯ぐきの炎症や出血を「よくあること」と軽視していませんか?実は、歯周病が進行している妊婦さんは、そうでない方に比べて早産や低体重児出産のリスクが高まるという研究結果が国内外で報告されています。歯周病による慢性的な炎症反応は、プロスタグランジンやサイトカインといった物質を体内で増加させます。これらは通常、分娩を促す働きを持つため、妊娠後期であれば出産につながりますが、妊娠中期以前に過剰に分泌されると子宮の収縮を早め、結果として早産のリスクを高めてしまう可能性があるのです。歯周病は自覚症状が出にくいため、痛みがなくても定期的な歯科健診でチェックを受けることが重要です。
妊婦健診だけでは見逃される口腔リスク
多くの方が妊娠中は産婦人科での妊婦健診を受けていますが、その内容は胎児の成長や血圧、尿検査などが中心で、口腔内の状態まではカバーしていないことが大半です。妊娠中はホルモンバランスの影響で唾液の分泌量や性質が変化し、歯垢や歯石がつきやすくなります。さらに、つわりなどの影響で歯磨きが不十分になることで、虫歯や歯周病が進行しやすい口腔環境になります。これらの変化は一見健康に見える口腔内でも静かに進行するため、自己判断では見つけにくいのが現実です。妊娠中期に歯科健診を受けることで、早期発見・早期処置が可能になり、安心して出産を迎えることができます。
母体‐胎児双方の健康を守るエビデンス
マタニティ歯科の重要性は、世界保健機関(WHO)やアメリカ疾病予防管理センター(CDC)、日本産科婦人科学会などの公的機関によっても提言されています。特に妊娠中期(16~27週)には、母体の体調が安定し、赤ちゃんの器官形成もほぼ終わっているため、歯科治療や口腔ケアを行うのに適した時期とされています。近年では、妊娠中に歯周治療を受けることで、血液中の炎症マーカーが低下し、全身状態の改善にもつながるというデータが報告されています。また、妊娠中の母親の口腔内が清潔であることは、生まれてくる赤ちゃんへの虫歯菌(ミュータンス菌)の感染リスクを減らすことにも貢献します。これは将来の乳歯の健康に直結するだけでなく、子どもの歯科通院に対する意識形成にもつながる大切なポイントです。
3.妊娠中に受けても安全な歯科治療・処置とは?

レントゲン撮影・麻酔・薬剤の安全基準(国内外ガイドライン)
「妊娠中にレントゲンを撮っても大丈夫ですか?」「麻酔や薬は赤ちゃんに影響しませんか?」といったご不安は、妊婦さんからよく寄せられる質問です。結論から申し上げると、国内外の歯科・産科のガイドラインにおいて、妊娠中でも適切な範囲で歯科治療を行うことは安全であるとされています。たとえば歯科用レントゲンは非常に微量の放射線しか使用しません。撮影時には鉛のエプロンで腹部を保護するため、胎児への影響はほぼないと考えられています。麻酔についても、局所麻酔薬は胎盤を通過しにくい性質があり、使用する薬剤と量を守れば母体にも胎児にも問題ないと報告されています。抗菌薬や鎮痛薬も、妊娠中に使用可能とされる種類があり、医師が状態を見て適切に選択します。重要なのは、自己判断で市販薬を使わないことと、痛みを我慢して症状を悪化させないこと。必要なときに適切な治療を受けることで、かえって赤ちゃんの健康リスクを減らせるのです。
安定期(妊娠中期)に行う虫歯・歯周病治療のポイント
妊娠中の歯科治療において「いつ受ければよいか」は非常に大切なポイントです。一般的に推奨されるのは妊娠中期(16〜27週頃)。この時期はつわりが落ち着き、母体の体調も比較的安定しています。また、胎児の主要な臓器の形成も完了しており、治療時に使用する麻酔や薬剤による影響リスクが低いとされています。虫歯治療やスケーリング(歯石除去)、初期の歯周病治療などは、このタイミングで計画的に進めるとよいでしょう。歯ぐきが腫れて出血しやすい妊娠性歯肉炎も、放置すると炎症が進行し、後期になって急激に悪化するケースもあります。歯周病は全身への影響もあるため、「後で受ければいい」と先送りせず、妊娠中期に必要な処置を済ませておくことが重要です。
避けた方がよい処置と応急処置の判断基準
一方で、妊娠中は避けるべき治療も存在します。たとえば、抜歯を伴う外科的処置や長時間に及ぶ治療、身体への振動が大きい処置(歯を削る量が多い補綴治療など)は、原則として緊急性がない限り産後に延期することが望ましいとされています。また、美容目的のホワイトニングやメタルフリー修復に使う強力な接着剤など、一部の薬剤は妊娠中の使用に明確な安全性が確立されていないものもあります。治療の必要性が高く、妊娠中にどうしても対応が必要な場合は、処置の回数を最小限に分割したり、体勢に配慮してチェアタイムを短くしたりすることで、母体への負担を軽減する工夫が取られます。応急処置で痛みや腫れを一時的に抑え、出産後に本格的な治療に移行するプランも一般的です。いずれの場合も、歯科医師が産科の主治医と連携しながら進めることが理想的です。
4.産後に先送りすると起こりやすいトラブル

授乳・寝不足によるママの免疫低下と急性症状
出産後は赤ちゃん中心の生活に変わり、まとまった睡眠が取れないことが多くなります。特に授乳中は、夜間の頻繁な授乳やホルモンバランスの変化により、母体の免疫力が一時的に低下しやすい状態にあります。こうした時期には、妊娠中に放置していた軽度の虫歯や歯周炎が急に悪化し、痛みや腫れを引き起こすことがあります。さらに、親知らずの腫れや膿瘍(のうよう)など、急性症状に発展することも。痛み止めや抗生物質の使用も授乳中は制限があるため、思うように治療が進まず、心身ともに負担が大きくなるケースが少なくありません。こうした背景からも、産後のトラブルを避けるには、妊娠中にできる処置をなるべく終わらせておくことが望ましいといえます。
育児多忙で歯科受診のタイミングを逃すリスク
産後は新生児の授乳・おむつ替え・寝かしつけなど、分刻みの育児に追われる日々が続きます。そのため、自分の通院やケアは後回しになりがちで、「歯が痛いけれど行く時間がない」「予約を取ったけれどキャンセルせざるを得なかった」といった事態が頻発します。また、赤ちゃんを連れての通院には心理的なハードルもあり、泣いてしまうことや授乳のタイミングが気になるなど、ママ自身が“行きづらさ”を感じてしまうことも一因です。このように受診のタイミングを逃すことで、歯の状態がさらに悪化し、最終的に大きな治療が必要になるケースもあります。予防の観点からも、妊娠中の余裕があるうちに口腔内の状態を整えておくことが、産後の生活をスムーズにするポイントになります。
産後のホルモン変動と歯ぐきの再炎症
出産後の女性の体は、ホルモンバランスが劇的に変化します。妊娠中に増加していたエストロゲンやプロゲステロンが急激に減少することで、体内の炎症反応が強く出やすくなり、歯ぐきの腫れや出血といった症状が再燃しやすくなります。また、産後に再発した歯周病は気づかぬうちに進行しやすく、放置すると骨吸収や歯の動揺(グラつき)など、重度のトラブルへつながることもあります。さらに、育児ストレスや睡眠不足が重なると、食いしばり・歯ぎしりといった習慣が強まり、歯や歯ぐきへのダメージを加速させる要因にもなります。これらのリスクを回避するためにも、出産前に口腔環境を整え、炎症の火種を可能な限り取り除いておくことが大切です。
5.妊娠中 vs 産後――歯科受診タイミングの最適解
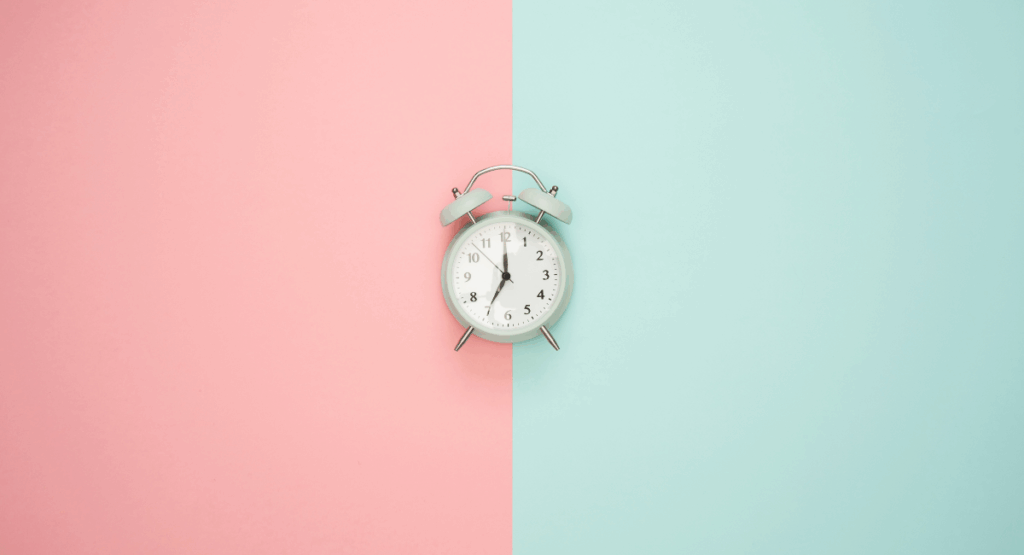
緊急性の有無で変わる治療優先度
歯科治療を「妊娠中に済ませるか」「産後に延期するか」を判断する上で最も重要なのは、その症状に緊急性があるかどうかです。たとえば、ズキズキと痛む虫歯や腫れを伴う歯ぐきの炎症は、放置すると悪化し、母体の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。こうした場合は、妊娠中であっても適切なタイミングを見極めて早めに処置を受けるべきです。一方で、美容目的の治療や緊急性の低い補綴(クラウン・ブリッジなど)は、産後に回すという判断も選択肢になります。歯科医は、レントゲンや歯周ポケット検査、問診などを通じて口腔内の状態を確認し、「今すぐ対応すべき治療」と「産後に延期可能な処置」を見極めたうえで、安全な治療計画を立てていきます。自己判断で「妊娠中だから治療は全部ダメ」と考えるのではなく、まずは専門家に相談することが大切です。
妊娠中に完結させるべき処置/産後に回して良い処置
妊娠中に完了させておくべき治療には、急性症状が出ている虫歯や歯周病の処置、親知らずの炎症管理、詰め物・被せ物の脱離の修復などが挙げられます。これらは放置すると痛みや感染のリスクが高まり、出産までの間に症状が急激に進行してしまうこともあるため、安定期を中心に速やかに対応すべきです。逆に、審美目的のセラミック治療、ホワイトニング、歯列矯正の調整などは、産後に体調が落ち着いてから行っても問題ありません。また、治療時間が長くなりがちな複数歯の補綴治療や義歯作製も、赤ちゃんとの生活がある程度整った段階で再開する方が母体への負担が少なく済みます。治療を先延ばしにする場合でも、仮歯や一時的な修復処置などで咀嚼や審美性を一時的に保つことも可能なので、遠慮なく相談しましょう。
歯科医と産科医の連携で決める安全なスケジュール
妊娠中に歯科治療を受ける際、安心して治療を進めるためには歯科と産科の情報共有・連携が不可欠です。たとえば、妊娠経過に特別な注意が必要な方(切迫流産・妊娠高血圧症候群など)では、歯科側が配慮すべき点も多くなります。このようなケースでは、あらかじめ産婦人科の主治医に診療情報提供書を作成してもらい、歯科に共有することで、より安全かつスムーズな治療が可能になります。とくに麻酔や投薬を必要とする場合には、産科主治医の確認を得ることで母体へのリスクを最小限に抑えることができます。現在では、妊産婦の歯科診療に対応するためのガイドラインも整備されつつあり、医科歯科連携が取りやすい体制も進んでいます。歯科医師に妊娠週数や体調の変化を正確に伝え、必要に応じて産科との連携を図ることが、妊娠期の安全な歯科診療には欠かせません。
6.歯科受診が赤ちゃんに与えるポジティブな影響

母体の口腔環境改善が乳幼児の虫歯リスクを下げる理由
赤ちゃんの虫歯は「生まれつきのもの」と誤解されがちですが、実際には、虫歯菌(特にミュータンス菌)は出生時には赤ちゃんの口の中には存在しておらず、主に母親など身近な大人からの接触によって感染することがわかっています。これを「母子伝播」と呼び、特に生後19か月〜31か月の時期(感染の窓)に注意が必要です。この時期に母親の口腔内環境が不衛生な状態だと、唾液や食器の共有、キスなど日常的なスキンシップを通じて、赤ちゃんに虫歯菌がうつる可能性が高くなります。逆に、妊娠中に歯周病や虫歯の治療を終え、日々のブラッシングやフロス、定期的なメンテナンスによって母体の口腔内を清潔に保つことで、赤ちゃんの虫歯発症リスクを大きく下げることができます。妊娠中の歯科受診は、単なる「自分のためのケア」ではなく、赤ちゃんへの最初の予防歯科と言えるのです。
母乳・離乳食期に役立つ“噛む力”と顎の発育サポート
生後間もない赤ちゃんの顎の発達や噛む力には、母親の口腔機能も大きく関係しています。たとえば、母乳育児では赤ちゃんが母乳を吸うときに、母親の乳首をしっかりとくわえ、舌と唇、顎を使って吸引する運動を繰り返します。このとき、母親が歯の痛みや炎症、咬合不良を抱えていると、授乳姿勢が安定せず、赤ちゃんがうまく吸えなかったり、哺乳に偏りが出たりする可能性があります。さらに、授乳期を過ぎて離乳食に移行する段階では、咀嚼の仕方や食べる姿勢は、親の行動を見て学ぶことが多く、特に母親の咬み方や口の使い方をよく観察しています。もし母親の口腔状態が悪く、片側だけで噛んでいたり、やわらかい物ばかりを食べていたりすると、それが赤ちゃんにとっての“正常”となり、顎の左右差や咬合力の未発達につながるおそれもあります。妊娠中から母親自身の咬合や口腔機能を整えておくことは、子どもの健全な顎の発育や咀嚼機能の形成にもつながる、長期的に見て重要なケアと言えるでしょう。
家族全体のむし歯菌コントロールを始める最適なタイミング
赤ちゃんの虫歯リスクを下げるためには、母親だけでなく、家族全員が虫歯菌のコントロールに取り組むことが非常に大切です。赤ちゃんにとっての身近な大人は、父親や祖父母、兄弟姉妹など複数存在します。これらの家族のうち誰か一人でも虫歯菌の保菌状態が悪いと、日常的なスキンシップや食器の共有を通じて菌が伝播する可能性が高くなります。妊娠中というタイミングは、家族全体が“赤ちゃんを迎える準備”として、予防歯科の第一歩を踏み出す絶好のチャンスです。歯科では、母親だけでなくパートナーや同居家族に対しても簡単な口腔チェックやクリーニング、セルフケアのアドバイスを行うことが可能です。また、唾液検査や細菌検査によって、家族全員の口腔内の状態を可視化し、必要な対策を講じることもできます。赤ちゃんを中心に家族全体の健康意識を高めることで、家庭内の虫歯予防力が飛躍的に高まり、結果的に赤ちゃんの将来の口腔トラブルを減らすことにつながります。
7.妊婦さんが安心できるクリニック選びのチェックリスト

妊娠期治療の経験と実績が豊富な歯科医師の有無
妊娠中の歯科治療は、通常の診療と異なる点が多くあります。たとえば、妊婦さん特有の体調の変動、使用できる薬剤や麻酔の制限、胎児への影響を考慮した診療方針など、多角的な判断が求められるため、妊娠期の患者様に対応した経験のある歯科医師の存在がとても重要です。経験豊富な医師であれば、妊娠週数に応じた治療可否の判断はもちろん、つわりや貧血、低血圧といった症状への配慮も含めた診療スタイルを確立しているため、より安全でスムーズな対応が期待できます。また、問診時に「妊娠中であることを伝えた際の反応」や「無理に治療を進めようとせず、説明が丁寧かどうか」なども判断の材料になります。公式サイトで「マタニティ歯科対応」などの記載があるか、もしくは電話や初診時に直接確認しておくと安心です。
バリアフリーや通院しやすい院内設備・体勢配慮
妊娠中は身体のバランスが崩れやすく、ちょっとした段差や長時間の同じ姿勢が大きな負担になることもあります。そのため、物理的に通院しやすい環境かどうかも、クリニック選びの重要なポイントです。たとえば、エレベーター付きのビルかどうか、階段の昇降が必要ないか、待合室やトイレが広めに設計されているか、などが該当します。診療室では、リクライニングチェアの角度調整が可能かどうか、長時間の処置中に体勢を変えるタイミングを設けてもらえるかも確認するとよいでしょう。また、妊娠中の診療に慣れたスタッフが在籍していれば、診療前後のサポートも含めて安心感が違います。通いやすさと居心地の良さは、継続的なメンテナンスにも大きく関わるため、院内環境は実際に足を運んでチェックしてみるのがおすすめです。
産科と情報共有できる紹介状・連携体制
妊婦さんの歯科治療では、産科との連携体制があるかどうかも大きな安心材料になります。とくに持病がある方や妊娠経過に注意が必要な方(高血圧症、切迫早産、糖尿病など)は、主治産科医との連携がスムーズなクリニックを選ぶことが望ましいです。多くの歯科医院では、必要に応じて紹介状を作成したり、産科からの指示書に基づいた治療計画を立てたりといった医療連携が行われています。産科医の判断で「この週数なら治療可能」「この薬剤は避けるべき」などの情報を歯科側と共有することで、より安全で的確な治療が可能になります。また、歯科医院側が妊婦健診の結果や使用中の薬剤に配慮し、体調に合わせた診療スケジュールを提案してくれる場合もあります。事前に、連携体制について問い合わせてみたり、医科歯科連携に関する取り組みをHPで紹介しているかを確認したりするのも、信頼できるクリニックを見つける手がかりとなります。
8.通院前に知っておきたいQ&A“よくある5つの疑問”

レントゲン被ばくは大丈夫?
妊娠中のレントゲン撮影については、多くの方が不安を抱くポイントですが、歯科で使用するデジタルレントゲンは非常に低線量で、被ばく量はごくわずかです。加えて、撮影時には鉛入りの防護エプロンを着用し、腹部や骨盤をしっかり保護することで、胎児への影響は限りなくゼロに近く抑えられます。実際、国内外の医療ガイドラインでも、歯科レントゲンは妊娠中でも必要に応じて使用してよいと明記されており、医師の判断に基づいて安全に運用されています。不安がある場合は遠慮なく相談し、事前に妊娠週数や体調を伝えることで、最適なタイミングでの撮影が可能です。
妊娠中でもホワイトニングはできる?
ホワイトニング剤に含まれる過酸化水素は、歯の表面の色素を分解する効果がありますが、妊娠中の安全性に関しては明確なエビデンスが確立されていません。また、ホワイトニング中は長時間口を開ける必要があり、体調不良やつわりの症状を悪化させる恐れもあります。歯ぐきの炎症や知覚過敏が起きやすい妊娠期には、ホワイトニングの刺激が強く出る場合があるため、ほとんどの歯科医院では妊娠中のホワイトニングは控えるよう案内されています。どうしても色味が気になる場合は、一時的なクリーニングや研磨によるステイン除去で対応する方法もありますので、出産後の体調が安定してから本格的な施術を受けるのが安心です。
授乳中に痛み止めや抗生剤を飲んでもいい?
授乳中に薬を使用する際の注意点は、薬剤が母乳に移行するかどうかという点です。一般的な歯科処方で使われる痛み止め(アセトアミノフェン、ロキソプロフェンなど)や抗生物質(ペニシリン系、セフェム系など)は、授乳中でも使用可能な薬剤として広く認められており、使用量と期間を守れば安全性が高いとされています。ただし、薬の種類によっては乳児に影響を及ぼす可能性があるため、処方時には必ず授乳中であることを歯科医師に伝えることが重要です。状況に応じて、母乳への移行が少ない薬を選択したり、服用後に授乳までの時間を調整するなどの対応も可能です。自己判断で市販薬を使用するのは避け、必ず医師に相談した上で服薬しましょう。
麻酔は赤ちゃんに影響しない?
歯科治療で用いられる局所麻酔は、胎盤をほとんど通過しない薬剤(リドカインなど)が使用されるため、妊娠中でも安心して処置を受けられるとされています。投与量もごく少量で、全身への影響は限定的です。さらに、歯科では部分的な麻酔が中心で、全身麻酔とは異なり母体の血流や心拍数にも大きな影響を与えません。ただし、過度な緊張や不安から血圧が変動することはあり得るため、リラックスして受けられるよう事前に気になることを質問しておきましょう。痛みを我慢して無麻酔で治療を受けることの方が、ストレスによってお腹の張りや体調不良を招くリスクがあるため、必要に応じて適切に麻酔を使う方が安全です。
つわりがひどい日はキャンセルしてもいい?
妊娠初期はつわりの影響で体調が安定しない日が多くあります。そのため、当日キャンセルや予約変更に柔軟に対応してくれる歯科医院かどうかも事前に確認しておくと安心です。とくに妊婦さんの診療に慣れている医院では、「無理をせず体調の良い日に来てください」といった柔軟な対応が一般的です。キャンセルや遅刻を気にして通院をためらうよりも、症状や不安を正直に伝えることが大切です。また、通院の際には体調が良くなる時間帯(午前中や食後など)を選んだり、診療前に軽く食事をとったりすることで、負担を減らす工夫も可能です。
9.受診からメンテナンスまでの流れとサポート体制

初診カウンセリングでの問診・同意のステップ
妊娠中に歯科を受診する際は、まず最初にしっかりとしたカウンセリングが行われることが安心につながります。初診時には、問診票に妊娠週数やつわりの有無、体調の変化、既往歴などを記入し、それをもとに歯科医師がヒアリングを行います。特に大切なのが「産科医の診断内容」や「服薬中の薬」などの情報。妊娠中は処置の内容が制限されることがあるため、正確な情報を共有することで、無理のない治療計画が立てられます。また、必要に応じて産婦人科との連携を図るケースもあります。問診の段階で不安や疑問点がある場合は遠慮なく伝えましょう。カウンセリングで十分な情報提供と同意(インフォームドコンセント)が得られていれば、その後の治療にも安心して臨むことができます。
妊娠期・産後別フォローアップと定期検診プラン
歯科医院では、妊娠の時期に応じて治療やケアの進め方が異なります。たとえば、妊娠初期(〜15週)はつわりの影響や流産のリスクに配慮し、緊急時を除いて治療は慎重に進めます。妊娠中期(16〜27週)は体調が安定し、治療に最も適した時期とされるため、虫歯や歯周病の治療、クリーニング、歯石除去などを中心に計画を進めることが一般的です。妊娠後期(28週以降)はお腹が大きくなるため、長時間の診療を避け、必要最低限の対応に留めるのが基本です。また、出産後は生活リズムの変化や授乳中の体調変化により、再び口腔トラブルが起こりやすくなるため、産後1〜3か月を目安に一度定期検診を受けることが推奨されます。このように、妊娠期・産後に合わせた段階的なフォローアップを提供してくれる歯科医院を選ぶことで、長期的な口腔管理がしやすくなります。
助産師・管理栄養士とのチームアプローチ例
最近では、「妊娠中の口腔ケア」を単なる歯科治療にとどめず、産科や栄養指導と連携してサポートする取り組みも増えてきました。たとえば、妊産婦外来と連携しているクリニックでは、助産師や管理栄養士がチームとして関与し、歯科と連携しながら総合的な妊婦支援を行うことがあります。助産師は妊娠の経過や母体のリスクを把握しているため、歯科治療の時期や姿勢へのアドバイスができ、管理栄養士は虫歯や歯周病予防に関わる食生活の改善提案を行うことで、より実践的なサポートが受けられます。また、栄養バランスの良い食事は歯ぐきの健康維持にもつながり、赤ちゃんの成長にも好影響を与えるとされています。こうした医科歯科連携の体制がある医院では、妊婦さんが安心して通える環境が整っており、医療の「つながり」の中で自分自身と赤ちゃんを守ることができるのです。
10.ママと赤ちゃんの未来を守る“今”できる第一歩

今日から始めるセルフケア3か条
妊娠中の口腔環境は、ホルモンバランスや体調の変化によって刻一刻と変わっていきます。そのため、妊娠がわかった段階から自分でできるケアを始めることが、赤ちゃんの健康を守る第一歩になります。まず一つ目は、「1日2回以上の丁寧なブラッシング」。とくに就寝前の歯磨きは重要で、寝ている間は唾液の分泌が減り、虫歯菌や歯周病菌が活発になるため、プラークを確実に除去する必要があります。二つ目は「デンタルフロスや歯間ブラシの活用」。妊娠中は歯ぐきの炎症が起こりやすく、歯と歯の間のプラークを放置すると出血や腫れの原因になります。三つ目は「フッ素配合歯みがき剤や洗口剤の併用」。酸への抵抗力を高め、脱灰(歯の表面が溶ける現象)を抑える効果があり、つわりなどでブラッシングが難しいときにも有効です。これらは、特別な道具を揃えなくても今日から始められる対策であり、妊娠初期から実践しておくことで、治療を必要としない状態をキープしやすくなります。
歯科受診をためらわないための心構え
「妊娠中は歯科に行ってはいけない」「麻酔やレントゲンは赤ちゃんに悪影響があるかもしれない」といった誤解が、妊婦さんの不安を大きくし、受診をためらわせる原因になることがあります。しかし、現在の歯科医療では、妊婦さんが安心して治療を受けられるよう、エビデンスに基づいた安全な診療体制が整備されています。レントゲンは低線量で腹部を防護し、麻酔も胎児に影響を与えにくい薬剤が選ばれ、必要最低限の量にとどめられます。また、治療中の体勢やチェアの角度、診療時間なども、母体の負担を減らすよう配慮されています。大切なのは、「痛みが出てから受診する」のではなく、「予防のために受診する」という意識を持つことです。自覚症状がなくても、妊娠中はトラブルが起こりやすい時期。専門家のチェックを受けることで、安心して妊娠期を過ごすことができます。
相談だけでもOK――妊娠期の不安を解消する窓口紹介
歯科受診というと「治療が必要なときに行く場所」と思われがちですが、実際には“相談するために行く場所”としても活用できます。妊娠中は初めて経験する体調の変化や症状に戸惑い、「これは歯科に関係あるのか分からない」「大げさかもしれない」と自己判断で我慢してしまうケースが少なくありません。しかし、歯ぐきの腫れや出血、口臭、虫歯のような違和感など、小さな変化でも気になったら相談する価値があります。多くの歯科医院では、妊婦さんのための無料カウンセリングや妊産婦検診を実施しており、必要があれば産科との連携やフォローアップまで対応してくれます。また、地域によっては保健センターや母子保健事業の一環で歯科相談窓口を設けていることもあるため、そうした行政のサポートも積極的に活用しましょう。誰かに相談するだけで不安が軽減され、結果的に健康管理への意識も高まるきっかけになります。
監修:愛育クリニック麻布歯科ユニット
所在地〒:東京都港区南麻布5丁目6-8 総合母子保健センター愛育クリニック
電話番号☎:03-3473-8243
*監修者
愛育クリニック麻布歯科ユニット
ドクター 安達 英一
*出身大学
日本大学歯学部
*経歴
・日本大学歯学部付属歯科病院 勤務
・東京都式根島歯科診療所 勤務
・長崎県澤本歯科医院 勤務
・医療法人社団東杏会丸ビル歯科 勤務
・愛育クリニック麻布歯科ユニット 開設
・愛育幼稚園 校医
・愛育養護学校 校医
・青山一丁目麻布歯科 開設
・区立西麻布保育園 園医
*所属
・日本歯科医師会
・東京都歯科医師会
・東京都港区麻布赤坂歯科医師会
・日本歯周病学会
・日本小児歯科学会
・日本歯科審美学会
・日本口腔インプラント学会

