妊婦健診の歯医者はいつ行くべき?安心して受けられる時期と注意点
「もしかして…」妊娠中の歯の悩み、一人で抱えていませんか?
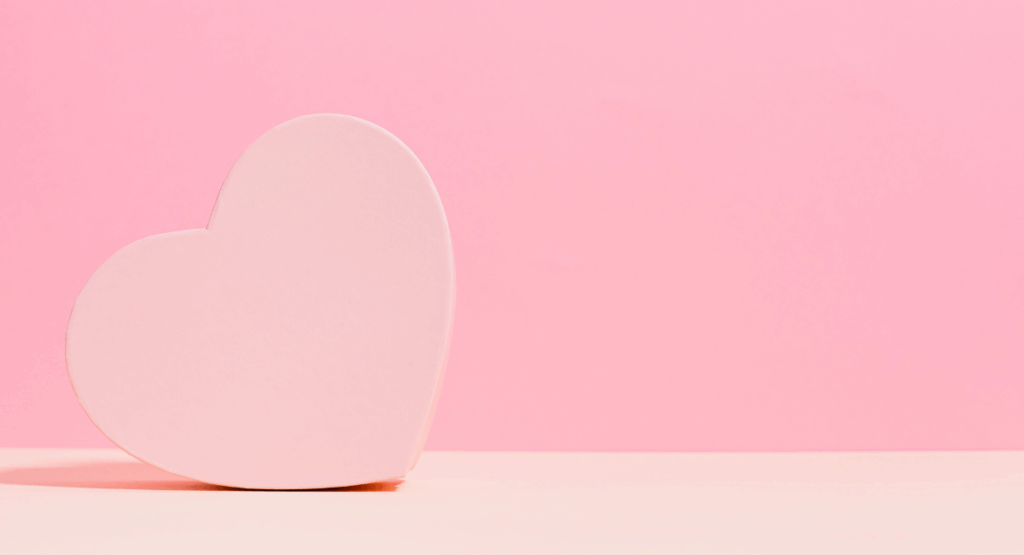
・つわりで歯磨きが辛い…これって私だけ?
妊娠初期から中期にかけて、多くの方が経験するつわりは、日常の口腔ケアにも影響を及ぼします。特に、歯ブラシを口に入れた瞬間に吐き気を感じる「刷毛反射」は珍しくなく、多くの妊婦さんが経験するといわれています。
この状態が続くと、歯垢や食べかすが残りやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。無理にしっかり磨こうとせず、ヘッドの小さい歯ブラシや、香りや味の弱い歯磨き粉を選ぶことで負担を軽減できます。
また、朝よりも体調の良い時間帯に短時間で小まめに磨く、どうしてもブラッシングが難しい日はフッ素入りの洗口液やうがいで代用するなど、柔軟な工夫も有効です。つわりが落ち着いたら、早めに歯科でクリーニングを受けることで、つわり中に蓄積した汚れを一掃できます。
・歯茎から血が出るけど、大丈夫?
妊娠中は女性ホルモンの影響で歯ぐきが腫れやすくなり、少しの刺激でも出血する「妊娠性歯肉炎」が起こりやすくなります。
これは一時的な症状のこともありますが、炎症が進行すると歯周病に移行するリスクがあります。歯周病は歯を支える骨を溶かすだけでなく、早産や低体重児出産のリスクを高める可能性が報告されており、放置は避けるべきです。出血があると歯磨きを控えたくなりますが、清掃不足は炎症を悪化させます。やわらかい毛の歯ブラシで力を入れずに磨き、フロスや歯間ブラシで汚れを取り除きましょう。
出血や腫れが2週間以上続く場合は、歯科医院での診査・クリーニングを受けることが大切です。
・まさか妊娠中に歯医者さんに行っていいの?
妊娠中でも、多くの歯科治療や予防処置を行うことが可能です。特に安定期(妊娠5〜7か月頃)は、母体・胎児ともに比較的落ち着いており、診療に適した時期とされています。むし歯や歯周病を放置すると症状が悪化し、妊娠後期に強い痛みや腫れを引き起こすこともあります。
妊娠初期や後期でも、緊急性の高い処置(痛みや感染の除去など)は必要に応じて行われますが、母体への負担を減らすため、治療計画は慎重に立てられます。
来院時は必ず妊娠中であること、妊娠週数、服薬中の薬や持病の有無を伝えましょう。X線撮影や薬の使用も、必要に応じて安全性を確保した方法が選ばれます。早めに相談し、安心できる治療環境を整えることが重要です。
なぜ妊娠中は歯のトラブルが起きやすいの?とりあえず知っておきたい3つの理由

・理由1:女性ホルモンの変化と歯周病菌
妊娠中はエストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンが増加し、歯周組織に影響を及ぼします。
これらのホルモンは歯周病菌の増殖や活性を促す作用があり、特に「プレボテラ・インターメディア(妊娠中に増えやすい歯周病菌の一種)」などの菌が繁殖しやすくなります。その結果、歯ぐきが腫れやすくなり、少しの刺激でも出血する「妊娠性歯肉炎」が起こりやすくなります。
放置すると歯周病へ進行し、重症化すれば歯を支える骨が溶けるだけでなく、早産や低体重児出産のリスクを高める可能性も指摘されています。妊婦健診と合わせて歯科健診を受け、必要に応じて早めに専門的なケアを行うことが大切です。
・理由2:つわりによる食生活の変化とむし歯リスク
つわりがあると、一度にしっかり食事をとることが難しくなり、空腹を避けるために間食や甘い飲み物の摂取が増える傾向があります。また、吐き気やえづきのために歯磨きが十分にできず、口腔内に糖質が長く残りやすくなります。
これらはむし歯菌が酸を産生する時間を延ばし、歯の表面のエナメル質を溶かすリスクを高めます。さらに、嘔吐によって胃酸が口腔内に逆流すると、歯の表面が酸で軟化し、むし歯や胃酸などで歯が溶ける病気(酸蝕症)の進行を助長します。
こうしたリスクを減らすためには、体調の良い時間帯に短時間でも歯磨きを行い、難しい場合は水やフッ素入り洗口液でうがいすることが有効です。
・理由3:唾液の性質の変化と自浄作用の低下
妊娠中はホルモンや自律神経の影響で唾液の分泌量や成分が変化することがあります。唾液は本来、口腔内を洗い流し、中和し、むし歯や歯周病から守る重要な役割を持っています。
しかし、妊娠中に唾液の分泌量が減少したり、粘性が高まったりすると、自浄作用が低下し、歯垢や食べかすが残りやすくなります。さらに、唾液中の抗菌成分が減少することで、口腔内の細菌バランスが崩れやすくなります。
これにより、むし歯や歯周病の発症リスクが上昇します。日常的に水分をこまめに補給し、唾液分泌を促すためにキシリトールガムを噛むなどの対策も有効です。
ママと赤ちゃんの未来のために。歯周病が及ぼす専門的なリスク

・早産・低体重児出産との関連性
近年の研究では、妊娠中の歯周病が早産や低体重児出産のリスクを高める可能性があることが報告されています。歯周病が進行すると、炎症部位から炎症を広げる物質である炎症性サイトカイン(プロスタグランジンE2やIL-6など)が血流に乗って全身へ拡散し、子宮収縮を促進する場合があります。
これにより予定より早く陣痛が始まったり、胎児の発育に影響を及ぼすことがあります。妊婦健診と同様に、歯科健診を受けて口腔内の炎症を早期にコントロールすることは、母体と胎児双方の健康を守る上で重要です。
特に安定期は治療や予防処置が行いやすい時期であり、この時期の受診が推奨されます。また、早産や低体重児を防ぐためには歯肉炎・歯周病の治療を受けることが大切です。さらに、可能な限り1か月ごとのクリーニングを継続し、体調を考慮して午前中の受診を選ぶことで、妊婦さんにとってより安心して治療を受けられる環境が整います。
・生まれた赤ちゃんへのむし歯菌の感染リスク
赤ちゃんは生まれた時点ではむし歯菌を持っていませんが、母親や家族から唾液を介して感染します。特に母親が歯周病やむし歯を抱えている場合、口腔内の細菌数が多く、感染のリスクが高まります。授乳期や離乳食期にはスプーンや箸の共有、口移しなどで菌が伝わりやすく、これが将来のむし歯リスクを左右します。
妊娠中から歯科医院でむし歯や歯周病の治療・予防処置を行うことは、出産後の赤ちゃんへの菌の伝播を減らすためにも有効です。母親の口腔環境を清潔に保つことが、赤ちゃんの健康な歯のスタートにつながります。
・産後のママ自身の健康への影響
産後は授乳や育児で生活が不規則になり、自分のケアが後回しになりがちです。この時期に歯周病が進行すると、歯の喪失だけでなく、糖尿病や心疾患など全身の健康リスクにも関与することが知られています。
特に妊娠中から歯周病を抱えていた場合、産後に症状が悪化しやすく、育児への体力や集中力にも影響を及ぼすことがあります。妊娠中に口腔内環境を整えておくことで、産後のトラブルを減らし、健康な状態で育児に専念できる環境を作ることが可能です。
妊婦健診と合わせて「歯医者はいつ行くべきか」を意識し、計画的に受診することが望まれます。
妊婦歯科健診、ベストタイミングは「妊娠中期(5~7ヶ月)」です

・なぜ「安定期」が歯科治療に最も適しているのか
妊娠中期(5~7ヶ月頃)は、母体と胎児の状態が比較的安定しており、歯科治療や予防処置を安全に行いやすい時期です。妊娠初期のつわりや体調不良が落ち着き、長時間の診療にも耐えやすくなります。
また、この時期は薬の使用やX線撮影が必要になった場合も、安全性に配慮した方法を選択しやすく、処置の選択肢が広がります。妊婦健診と同様に、このタイミングで歯科健診を受けることは、出産までの間にトラブルを予防する重要な機会です。
特に歯周病やむし歯は、放置すると出産前後の健康に影響するため、安定期での受診が推奨されます。
・妊娠初期(~4ヶ月)にできること・控えるべきこと
妊娠初期は胎児の重要な器官が形成される時期であり、母体もつわりや倦怠感などで体調が不安定になりやすい時期です。このため、緊急性のない治療は控え、検診や口腔清掃など負担の少ないケアを中心に行います。
ただし、強い痛みや感染症状がある場合は、母体の健康を守るためにも必要な治療が優先されます。診療時間は短めに設定し、姿勢の変化や体調変動に配慮することが大切です。妊婦健診の際に「歯医者はいつ行くべきか」を相談し、治療の必要性や時期を医師と歯科医師で連携して判断すると安心です。
・妊娠後期(8ヶ月~)に急な痛みが出た場合の対処法
妊娠後期はお腹が大きくなり、長時間仰向けの姿勢を取ることが難しくなるため、計画的な治療には不向きです。しかし、急な歯の痛みや腫れなど緊急性の高い症状が出た場合は、我慢せずに歯科医院へ連絡しましょう。
応急処置で痛みや感染を抑え、出産後に本格的な治療を行うケースが多くあります。診療中は身体の左側をやや下にした姿勢をとるなど、母体と胎児への負担を減らす工夫が必要です。自己判断で市販薬を服用せず、必ず主治医と歯科医師の両方に相談してから対応することが安全です。
妊娠中の歯科治療、できないの?

・むし歯や歯周病の「応急措置」と「本格的な治療」
妊娠中でも、多くの場合は歯科治療を受けられます。ただし、妊娠時期や症状の程度によって、治療内容や進め方が変わります。急な痛みや腫れがある場合は、妊娠初期や後期でも応急処置を行い、症状を和らげることが優先されます。
一方で、長時間の治療や外科的処置が必要な場合は、母体と胎児への負担が少ない妊娠中期(安定期)に計画的に行うのが一般的です。妊婦健診と同様に、「歯医者はいつ行くべきか」を主治医と歯科医師で相談し、最適な治療時期を決めることが安心につながります。
・胎児への影響が少ない「局所麻酔」の考え方
妊娠中の歯科治療で用いられる局所麻酔は、適切に使用すれば胎児への影響は少ないとされています。一般的に歯科で使用されるリドカインという麻酔は、安全性が高く世界的にも広く使われています。必要な範囲で局所的に作用するため、全身への影響は最小限です。
また、痛みを我慢して治療を受けることはストレスや血圧上昇につながり、かえって母体と胎児に負担をかける場合があります。麻酔を使う際は、妊娠していることや週数を必ず歯科医に伝え、安心できる環境で処置を受けることが大切です。
・防護エプロン着用で行う「レントゲン撮影」の安全性
歯科でのレントゲン撮影は、口腔内の状態を正確に診断するための手段の1つです。使用される放射線量は非常に少なく、防護エプロンを使用すれば胎児への影響はごくわずかとされています。
特にデジタルレントゲンは従来よりも被ばく量が大幅に少なく、安全性が高いとされています。必要な診断を避けてしまうと、見落としや治療の遅れにつながる可能性があります。妊娠中でも医師が必要と判断した場合は、安全対策を講じたうえで撮影を行うことが推奨されます。
・妊娠時期に合わせて処方される「お薬」について
妊娠中に使用できる薬は限られていますが、歯科治療で必要な場合には胎児への影響を考慮した安全性の高い薬が選ばれます。
例えば、痛み止めではアセトアミノフェンが比較的安全とされ、抗生物質ではペニシリン系やセフェム系がよく用いられます。妊娠初期や後期は薬の影響を受けやすいため、用量・使用期間も最小限に抑えられます。自己判断で市販薬を服用せず、必ず主治医や歯科医師に相談のうえで処方を受けることが重要です。
後悔しないために。妊婦歯科健診を受ける医院選びの3つのポイント

・「マタニティ歯科」に関する知識と経験が豊富か
妊婦歯科健診では、妊娠期特有の口腔内変化や治療上の注意点を理解していることが不可欠です。妊娠中はホルモンの影響で歯ぐきが腫れやすくなり、つわりや食生活の変化でむし歯や歯周病のリスクが高まります。
こうした背景を理解し、妊婦特有の症状に合わせた診療ができる歯科医院を選ぶことが大切です。また、妊娠中の安全な麻酔や薬の選択、レントゲン撮影時の防護など、エビデンスに基づいた対応ができるかも重要です。
初めて受診する場合は、医院のホームページで妊婦対応の実績や方針を確認したり、問い合わせ時に「妊娠中の患者さんへの対応経験があるか」を尋ねると安心です。
・産婦人科医と連携できる体制が最適
妊娠中の歯科治療は、母体と胎児の健康状態を十分に把握しながら行う必要があります。特に治療計画や薬の使用には慎重な判断が求められるため、産婦人科医と連携できる歯科医院は安心感が高いです。
例えば、妊婦健診で得た血圧や貧血の有無、妊娠経過の情報を歯科と共有することで、安全性の高い治療方針を立てられます。
また、急な痛みや感染症状が出た場合でも、主治医との連絡体制が整っていれば迅速に対応可能です。「妊婦健診と歯医者はいつ受けるべきか」を医科と歯科の両方からアドバイスしてもらえるのもメリットです。
・身体に負担の少ない体勢など、設備や環境への配慮があるか
妊娠後期になると、お腹の大きさや姿勢による圧迫感で、通常の診療チェアでの仰向け姿勢がつらくなることがあります。妊婦に配慮した医院では、チェアの角度を緩やかにしたり、背中や腰にクッションを使用する、左側を下にした横向き姿勢(左側臥位)を取るなど、体への負担を減らす工夫がされています。
また、診療時間を短く区切る、移動しやすいバリアフリー設計、温度や湿度の管理なども重要なポイントです。こうした配慮が整っている医院を選ぶことで、妊娠中でも安心して受診でき、健診や治療を計画的に進められます。
健診当日に向けて。準備しておきたいこと・必ず伝えてほしいこと
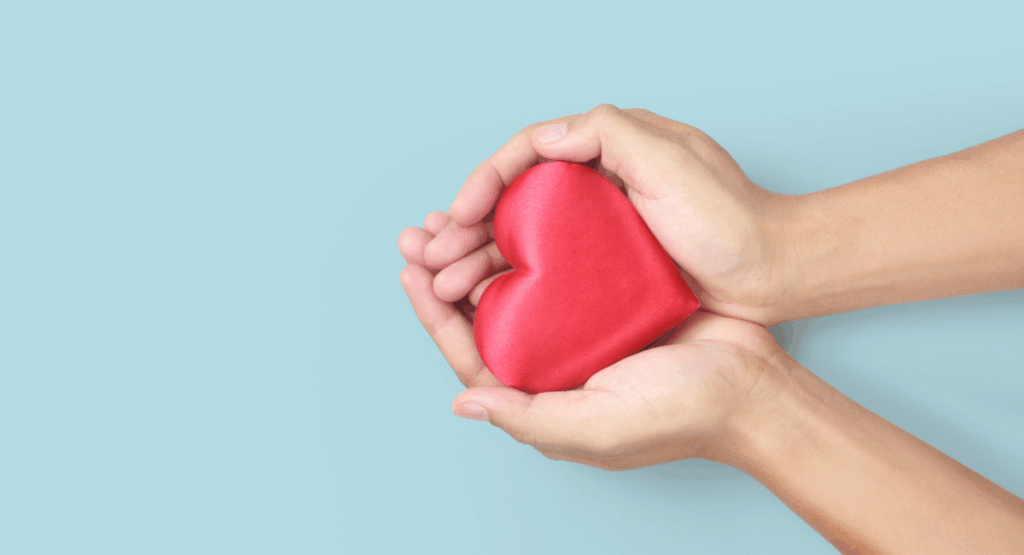
・忘れずに持参するもの:母子手帳と健康保険証
妊婦歯科健診を受ける際には、母子手帳と健康保険証の持参が必須です。母子手帳には妊娠週数や健診結果、妊娠経過の記録が残っており、歯科医師が診療内容を決めるうえで欠かせない情報源となります。特に、血圧や体重の推移、貧血の有無、合併症の記録などは、診療の可否や治療計画の判断に直結します。
また、健康保険証は保険診療を受けるために必要であり、急な処置や投薬が必要になった場合にも提示が求められます。
可能であれば、現在服用している薬やサプリメント、これまでの歯科治療履歴を書き出して持参すると、より正確で安全な対応が可能になります。
・予約時・問診票で必ず伝えるべき4つの項目
妊婦健診と歯科受診を安全に行うためには、受診前の情報提供が非常に重要です。
特に①妊娠週数、②妊娠経過の状況(切迫早産や流産予防の指示、安静の必要性など)、③持病や服薬状況(産婦人科から処方されている薬を含む)、④アレルギーや過去の副作用経験は必ず正確に伝えましょう。
これらの情報があれば、歯科医師は診療時間の長さ、チェアの角度、麻酔や薬の安全性、治療優先順位を適切に判断できます。情報が不十分だと、診療中に体調不良を起こすリスクが高まるため、些細なことでも正直に申告することが大切です。
・不安な気持ちを整理する「質問リスト」のススメ
妊娠中の歯科受診では、「治療は本当に安全か」「薬や麻酔は赤ちゃんに影響しないか」「出産までに治したほうがいい症状はあるか」など、多くの不安や疑問が浮かびやすくなります。
当日スムーズに相談できるよう、事前に質問リストを作っておくことをおすすめします。例えば、治療の必要性や時期、応急処置と本格治療の違い、授乳中の注意点なども含めて整理しておくと、限られた診療時間を有効活用できます。
また、質問しやすい雰囲気の医院を選ぶことも安心につながります。こうした準備は、妊婦健診と歯医者を「いつ」「どのタイミングで」受けるべきかの判断にも役立ちます。
【疑問を徹底的】妊婦歯科健診のよくある質問(FAQ)
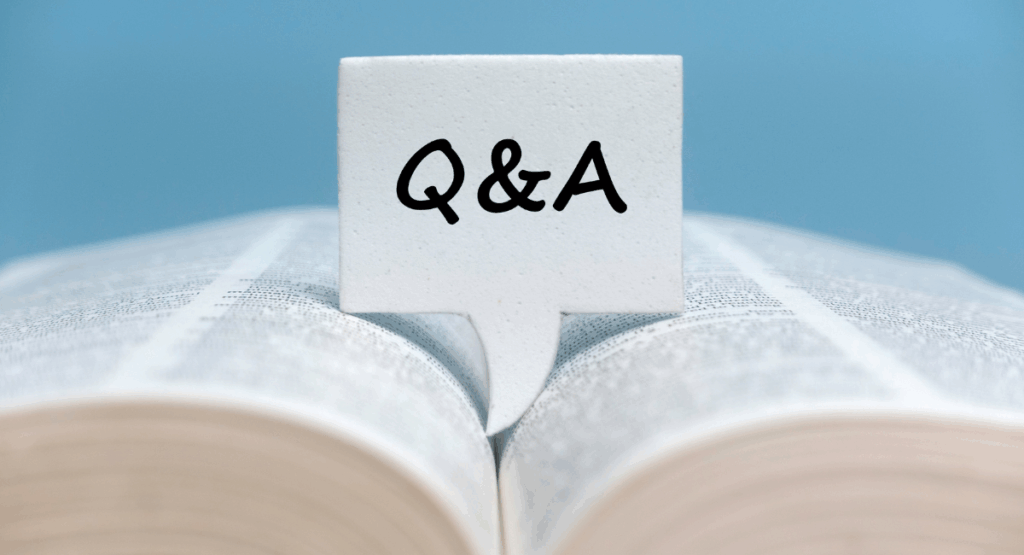
・自治体の「妊婦歯科健康診査受診券」は使うべき?
多くの自治体では、妊娠中の口腔環境を守るため「妊婦歯科健康診査受診券」や無料・一部負担の健診制度を設けています。これを利用すれば、歯科医師による口腔診査や歯周病リスクチェック、歯磨き指導などが費用負担なく受けられる場合があります。
妊娠中は歯周病やむし歯の進行が早まる傾向があり、早期発見・予防のためにも活用がおすすめです。使用期限や対象医院が決まっていることが多いため、母子手帳交付時に配布される案内や自治体の公式サイトで条件を確認し、妊婦健診と同様に「歯医者はいつ行くべきか」を計画的に検討しましょう。
・治療費はどれくらい?保険は適用される?
妊娠中でも、通常の歯科治療と同様に健康保険が適用されます。むし歯治療、歯周病治療、応急処置、レントゲン撮影、薬の処方など、必要な診療は3割負担(妊婦本人の場合)で受けられます。自治体の妊婦歯科健診は健診部分が無料となることがありますが、実際に治療を行った場合は別途保険診療として費用が発生します。
自由診療(セラミック、インプラントなど)は保険適用外となり全額自己負担です。費用の目安や支払い方法は事前に医院へ確認すると安心です。
・親知らずが痛い場合、歯は抜けますか?
妊娠中でも、感染や強い痛みがある場合は親知らずの抜歯を行うことがあります。特に膿が溜まっている場合や繰り返し腫れる場合は、放置すると母体や胎児への影響が懸念されるため、安定期(妊娠5〜7か月)に処置するケースが多いです。
妊娠初期や後期は必要に応じて応急処置にとどめ、出産後に抜歯を検討することもあります。局所麻酔やレントゲンは適切な方法で行えば安全性が確保されるため、自己判断せず歯科医師と産婦人科医に相談して治療時期を決めましょう。
・ホワイトニングやインプラントは受けられますか?
妊娠中は、ホワイトニングやインプラントなどの自由診療は基本的に推奨されません。ホワイトニングは薬剤による刺激や長時間の処置姿勢が負担になる可能性があり、インプラントは外科的処置や投薬が必要となるため、母体・胎児への安全性の観点から出産後に行うのが望ましいです。
妊娠中はまずむし歯や歯周病の予防・治療に専念し、見た目や機能回復を目的とした処置は産後の体調が安定してから計画すると安心です。
無事に出産を迎えました、その先へ。産後も見据えたお口の健康

・出産前に治療を終えることのメリット
妊娠中に必要な歯科治療を終えておくことは、母体と赤ちゃんの健康の両面でメリットがあります。産後は授乳や育児で生活リズムが不規則になり、歯科受診の時間を確保するのが難しくなります。
そのため、妊娠中期(安定期)にむし歯や歯周病、親知らずの炎症などを治療しておくと、産後の急な痛みや感染症リスクを減らせます。
また、出産後のホルモン変動や疲労は免疫力低下を招き、口腔トラブルが悪化しやすいため、事前のケアが予防につながります。妊婦健診と合わせて「歯医者はいつ行くべきか」を意識し、計画的に治療を進めることが大切です。
さらに、妊娠を考えている段階から歯科健診を受けておくことも重要です。妊娠が分かったらできるだけ早く歯科健診を受け、安心して妊娠期を過ごせるよう準備しましょう。
・赤ちゃんにむし歯をうつさないために、今からできること
赤ちゃんは生まれた時点ではむし歯菌を持っていませんが、親や周囲の大人から唾液を介して感染します。
特に母親の口腔内にむし歯や歯周病がある場合、細菌数が多く、感染リスクが高まります。スプーンや箸の共有、口移しなどの行為を避けることはもちろん、出産前から口腔環境を清潔に保ち、細菌数を減らしておくことが重要です。
妊娠中に定期的な歯科クリーニングや歯石除去を受けることで、母子ともに健康な口腔環境を維持しやすくなります。これは赤ちゃんの将来のむし歯予防にも直結する習慣です。
また、むし歯菌の感染を防ぐためには、お母さんだけでなくお父さんを含め、子育てに関わるご家族全員の口腔ケアが欠かせません。家族ぐるみで歯科健診を受け、清潔な口腔環境を整えることが赤ちゃんの健やかな成長につながります。
・産後のご自分のケアと、定期検診の新たなスタート
出産後は育児に追われ、自分の口腔ケアが後回しになりがちですが、産後こそ定期的な歯科健診が必要です。授乳や夜間対応による睡眠不足、食生活の乱れ、ホルモンバランスの変化は歯周病やむし歯のリスクを高めます。
産後1〜3か月を目安に、母体の体調が落ち着いたら歯科健診を再開するとよいでしょう。歯科医師による専門的なケアを受けることで、産後の健康維持はもちろん、赤ちゃんに安心して接することができます。
出産前後を通じてお口の健康を守ることは、母子の生活の質を高める大切な投資です。
まとめ:不安な気持ちは「まず相談」で、安心に変わります

・我慢や自己判断せず、専門家を頼りましょう
妊娠中の歯のトラブルは、痛みが軽くても放置すると短期間で悪化することがあります。「妊娠中だから歯医者に行けない」と思い込んで自己判断で様子を見ることは、母体だけでなく胎児の健康にも影響を及ぼす可能性があります。
例えば、歯周病は早産や低体重児出産のリスク要因とされ、むし歯の進行は急な痛みや感染症を引き起こします。妊婦健診と同様に、歯医者はいつ行くべきかを専門家と相談することで、適切なタイミングと安全な方法で治療や予防が可能になります。
・あなたの状態を正しく知ることが、最適なケアへの第一歩
自分では健康だと思っていても、歯周病やむし歯の初期段階は自覚症状がほとんどありません。妊娠中はホルモンや生活習慣の変化によって、短期間で症状が進行することもあります。妊婦歯科健診を受ければ、口腔内の現状やリスクを客観的に把握でき、必要に応じたケア計画を立てられます。
早期発見・早期対応により、治療期間や母体への負担を最小限に抑えることができるため、まずは正確な診断を受けることが重要です。
・健やかなマタニティライフと、お子様の未来のために
お口の健康は、妊娠中の快適な生活だけでなく、生まれてくる赤ちゃんの健康にも影響します。母親の口腔内環境が良好であれば、赤ちゃんへのむし歯菌の感染リスクを減らすことができ、将来的な歯の健康にもつながります。
妊娠中の歯科受診は、安全に配慮しながら行えるものが多く、適切なタイミングでの健診と治療は安心な出産準備の一環です。「妊婦健診と歯医者はいつ行くべきか」を意識し、計画的な受診で母子ともに健やかな未来を守りましょう。
監修:愛育クリニック麻布歯科ユニット
所在地〒:東京都港区南麻布5丁目6-8 総合母子保健センター愛育クリニック
電話番号☎:03-3473-8243
*監修者
愛育クリニック麻布歯科ユニット
ドクター 安達 英一
*出身大学
日本大学歯学部
*経歴
・日本大学歯学部付属歯科病院 勤務
・東京都式根島歯科診療所 勤務
・長崎県澤本歯科医院 勤務
・医療法人社団東杏会丸ビル歯科 勤務
・愛育クリニック麻布歯科ユニット 開設
・愛育幼稚園 校医
・愛育養護学校 校医
・青山一丁目麻布歯科 開設
・区立西麻布保育園 園医
*所属
・日本歯科医師会
・東京都歯科医師会
・東京都港区麻布赤坂歯科医師会
・日本歯周病学会
・日本小児歯科学会
・日本歯科審美学会
・日本口腔インプラント学会

