授乳中の歯医者、麻酔は大丈夫?お母さんと赤ちゃんの安心を第一に考える歯科治療
「痛いのはイヤ、でも赤ちゃんへの影響は?」授乳中の麻酔、最大の悩み

「歯が痛い…」治療したい気持ちと、授乳への不安との間で
「歯がズキズキ痛むけれど、歯医者に行ってもいいのだろうか」「治療はしたい、でも麻酔が母乳に影響したらどうしよう…」。授乳期間中のお母様が歯科治療をためらわれるとき、その胸にはご自身の痛みと、愛する赤ちゃんへの想との間で、こうした深い葛藤があることと思います。
特に出産後は、ホルモンバランスの変化や育児による生活リズムの乱れから、お口のトラブルが起きやすい時期でもあります。痛みを我慢しながらの育児は、心身ともに大きな負担となります。そのお気持ちに、私たちは専門家として静かに寄り添いたいと考えています。
ママの健康と、赤ちゃんの健やかな成長、どちらも大切にしたい
お母様の健康と、赤ちゃんの健やかなご成長は、決して切り離して考えられるものではありません。お母様が歯の痛みや不快感を我慢し、強いストレスにさらされ続けることは、ご自身の心身を消耗させるだけでなく、穏やかな気持ちで赤ちゃんと向き合う時間を損うことにも繋がりかねません。
むし歯や歯周病を放置すれば、症状が悪化し、より大掛かりな治療が必要になる可能性もあります。授乳中の今、ご自身の体を大切にケアすることは、赤ちゃんのためにもなる非常に重要な選択です。ママの健康的な笑顔こそが、赤ちゃんの健やかな成長の礎となるのです。
その不安、正しい知識で「安心」に変えましょう
授乳中の歯医者での麻酔に関する不安の多くは、「よくわからない」という漠然とした恐怖から生まれています。
幸いなことに、現代の歯科医療で通常使用される局所麻酔薬は、母乳への影響が非常に少ないことが科学的に明らかになっており、多くの専門機関がその安全性を認めています。この後の章で、なぜ安全と言えるのか、その専門的な根拠を一つひとつ丁寧に解説していきます。
正しい知識は、漠然とした不安を、納得できる「安心」に変える力を持っています。どうぞこのまま読み進めて、ご自身の状況を正しく理解することから始めてみてください。
まずは知っておきたい、歯科麻酔の基礎知識

歯科治療で使う「局所麻酔」とは?
歯科治療で用いられる麻酔は、全身麻酔とは異なり、治療する歯の周辺など、限られた範囲の感覚を一時的に麻痺させる「局所麻酔」です。意識がなくなることはなく、会話もできます。
この麻酔は、治療中の痛みを感じる神経の伝達をブロックすることで、患者様が痛みを感じることなく、安全・快適に治療を受けられるようにするために行います。日本で授乳中の歯医者の麻酔として最も一般的に使用されるのは「リドカイン」という薬剤で、血管収縮薬が添加されています。
これは麻酔薬が治療部位に長く留まり、効果が安定して持続するようにするためです。これまでの多くの臨床経験から、授乳中でも安全に使えると考えられています。
なぜ麻酔が必要?痛みを我慢するリスク
「少しの痛みなら我慢すれば…」とお考えになるかもしれませんが、実は痛みを我慢すること自体が、お母様の体に大きなストレスを与えます。強い痛みを感じると、体は防御反応として血圧を上昇させ、心拍数を増加させます。
このような急激な変化は、お体にとって大きな負担となります。特に、授乳中のお母様にとって過度なストレスは、母乳の分泌に影響を与える可能性も指摘されています。歯科麻酔は、こうした痛みのストレスからお母様を守り、心身ともにリラックスした状態で、より安全かつ精密な治療を行うために不可欠な処置なのです。
歯科医師は、麻酔を使うメリットがリスクを上回ると判断した場合にのみ、使用を提案します。
麻酔薬はどのように体からなくなるの?
局所麻酔薬は、注射した部位で作用した後、ゆっくりと血液中に吸収されます。血流に乗った麻酔薬は、主に肝臓で分解され、無毒化された後に、腎臓でろ過されて尿として体外へ排出されます。
つまり、体内に長く留まり続けることはありません。リドカインは、体内で半分に分解されるまでの時間(半減期)が約1.5〜2時間と短く、体に長く残りません
これは、比較的速やかに体内から消失していくことを意味します。歯科医師は、患者様のお体の状態を考慮し、効果が持続し、かつ安全に代謝・排泄される量の麻酔薬を正確にコントロールして使用しています。
なぜ安全と言えるのか?専門的な根拠を分かりやすく解説

理由1:作用する場所が限定的(局所性)
歯科治療で用いる麻酔が安全な最大の理由の一つは、その作用が「局所」、つまり治療する場所の周辺に限られる点にあります。麻酔薬に含まれる血管収縮薬(エピネフリン)が、注射した部分の血管を一時的に細くします。
これにより、麻酔薬はその場に留まり、血流に乗って全身に広がることが効果的に抑制されます。
全身に広がる薬の量がごくわずかであるため、当然、母乳を作る乳腺に到達する量も非常に少なくなります。この「局所性」という性質が、授乳中の歯医者での麻酔の安全性を支える、 fundamental な柱となっているのです。
理由2:体からの排出が非常に速い
お母様の体内に入ったごく微量の麻酔薬も、そこに長く留まることはありません。薬の血中濃度が半分になる時間を示す「半減期」という指標があり、歯科で主に使われるリドカインの半減期は1.5〜2時間と非常に短いことが特徴です。
これは、注射後2時間もすれば、血中に吸収された麻酔薬の半分が既に分解・代謝されていることを意味します。数時間後には、ほとんどの薬剤が肝臓で分解され、体外へと排出されてしまいます。
このように速やかに体から消失していく性質のため、母乳への影響も極めて短時間かつ一過性のものであり、過度に心配する必要はないと考えられています。
理由3:赤ちゃんが母乳から摂取する量は治療量の1%未満
母乳を介して赤ちゃんに薬剤がどの程度移行するかを示す指標に「相対的乳児投与量(RID)」があります。これは、お母様の体重あたりの投与量に対して、赤ちゃんが母乳から摂取する薬剤の量が何%にあたるかを示したものです。歯科で用いる局所麻酔薬リドカインのRIDは1%未満と報告されております。
つまり、お母さんに使った量のうち、赤ちゃんが母乳から取り込むのは1%にも満たないというごくわずかな量であり、これは安全性が高いということを示します。
仮に赤ちゃん自身に何らかの治療でリドカインを使用する場合の投与量と比較しても、母乳から摂取する量は遥かに微量であり、薬理学的な作用を及ぼすことは考えられません。この定量的なデータが、安全性の強力な裏付けとなっています。
授乳中でも受けられる歯科治療、先延ばしにしない方が良い治療とは?

むし歯治療:痛みがなくても静かに進行するリスク
「痛くないからまだ大丈夫」と思っていても、むし歯は静かに進行しています。特に産後は、食事の回数が増えたり、育児で疲れて歯磨きが不十分になったりしがちで、むし歯のリスクが高まる時期です。
小さなむし歯のうちに治療すれば、簡単な処置で済み、麻酔を使わずに済むこともあります。しかし、痛くなってからでは神経の治療が必要になるなど、治療が複雑化し、通院回数も増えてしまいます。授乳中の限られた時間の中で、心身ともに負担の少ない治療で終えるためにも、症状がない段階での早期発見・早期治療が何よりも大切です。
歯周病治療:お母様のお口の健康が赤ちゃんに与える影響
産後はホルモンバランスの影響で、歯ぐきが腫れやすく、歯周病が進行しやすい状態にあります。歯周病はお母様自身の問題だけでなく、実は赤ちゃんの健康にも関わっています。
生まれたばかりの赤ちゃんのお口には、むし歯菌や歯周病菌は存在しません。これらの細菌は、お箸やスプーンの共有などを通じて、最も身近な保護者から感染することが多いのです(母子感染)。
お母様がお口の中を清潔に保ち、歯周病菌の数を減らしておくことは、赤ちゃんへの細菌感染のリスクを低減させ、将来のお口の健康を守ることに繋がります。
親知らずの抜歯:育児中の急な痛みに備えるという選択肢
親知らずは、育児で心身ともに疲れている時に限って、急に腫れたり痛んだりすることがあります。これを「智歯周囲炎」と呼びます。夜間の激痛や、食事がとれないほどの強い腫れは、育児中の生活に大きな支障をきたします。
授乳中の歯医者では、もちろん麻酔を使って痛みのない抜歯が可能ですが、問題が起きてからの緊急対応よりも、状態が落ち着いている時に計画的に抜歯を行う方が、心身のご負担は遥かに少なくて済みます。歯
科健診などで抜歯を勧められている場合は、育児が少し落ち着いたタイミングで、計画的に治療を受けることも賢明な選択肢の一つです。
緊急性の低い治療(ホワイトニングなど)との上手な付き合い方
歯科治療には、むし歯や歯周病のような可及的速やかに治療すべきものと、ホワイトニングや一部の審美治療のように、緊急性の低いものがあります。
授乳中のホワイトニングは、使用する薬剤が赤ちゃんに有害であるという明確なエビデンスはありませんが、逆に「絶対に安全である」という十分なデータもまだ蓄積されていません。
そのため、多くの歯科医院では「安全を第一に考える」という原則に基づき、授乳期間が終了してからの施術をお勧めしています。まずは優先度の高い治療をしっかりと行い、お口の健康状態を整えることを第一に考えましょう。
安心して治療を受けるために、お母さんができること

必ず「授乳中であること」を歯科医師に伝える
安全な治療のための最も重要で、かつ基本的な第一歩は、予約時や問診票を記入する際に、必ず「授乳中であること」を明確に伝えることです。産後の経過や赤ちゃんの月齢なども併せてお伝えいただくと、より細やかな配慮が可能になります。
授乳中であることを歯科医師が把握することで、麻酔薬はもちろん、治療後に処方される可能性のある痛み止めや抗生物質の種類と量についても、母乳への影響を最小限に抑える最適なものを選択できます。
これは、お母様と赤ちゃん双方の安全を確保するための、医療者と患者様との大切な情報共有です。遠慮なく、まずはお申し出ください。
治療を受けるタイミングは?授乳直後がおすすめ
歯科麻酔の母乳への影響は極めて少ないため、基本的にはどのタイミングで治療を受けても問題ありません。
しかし、それでも少しでも不安を減らしたい、というお母様には「授乳直後」の時間帯に予約を取ることをお勧めしています。治療の直前に授乳を済ませておくことで、次の授乳までにある程度の時間を確保できます。
歯科麻酔薬の血中濃度は、使用後1〜2時間でピークを迎え、その後は急速に低下していきます。次の授乳時間までの間隔を最大限に空けることで、血中濃度がより低くなった状態で授乳できるため、お母様の心理的な安心に繋がります。
不安なことは、どんな些細なことでも質問する
専門的な知識に基づいて「安全です」と説明されても、お母様ご自身の心の中に少しでも疑問や不安が残っていては、心から安心して治療を受けることはできません。私たち医療者にとって、患者様の不安を解消することも、治療と同じくらい大切な責務です。
「今日使う麻酔薬の名前はなんですか?」「念のため、何時間くらい空けて授乳すればより安心ですか?」など、どんなに些細だと感じることでも、遠慮なくご質問ください。
一つひとつの疑問に丁寧にお答えし、ご自身が心から納得した上で治療に進むことが、何よりも大切だと考えています。
赤ちゃんと一緒に通える歯医者さんの選び方と、当日の準備

事前確認が安心の鍵。「マタニティ歯科」の視点を持つ医院
授乳中に安心して歯科治療を受けるためには、医院選びが非常に重要です。医院のホームページなどで「マタニティ歯科」や「産前・産後の歯科治療」について言及があるかを確認してみましょう。
このような医院は、授乳中の麻酔や薬の安全性に関する知識が豊富で、お母様方の不安や疑問に寄り添う体制が整っていることが多いです。
予約の電話の際には、「現在授乳中なのですが、赤ちゃんを連れての通院は可能ですか?」と一言添えてみてください。その際の電話対応の丁寧さも、医院の姿勢を知る上での良い判断材料になります。
ベビーカーでの来院は可能?院内設備や予約時間もチェック
赤ちゃんを連れて通院する場合、院内の設備は快適さを左右する大きなポイントです。医院の入口にスロープがあってベビーカーでそのまま入れるか、院内にベビーカーを置くスペースはあるか、といった点は事前に確認しておくとスムーズです。
また、おむつ交換台やキッズスペースの有無も確認しておくと、いざという時に安心です。予約時間については、比較的空いている平日の午前中や、赤ちゃんのお昼寝の時間帯を狙うなど、ご自身のペースに合った時間帯を相談してみるのも良いでしょう。
少しでもお母様の負担が軽くなるような配慮をしてくれる医院を選びましょう。
パートナーや家族との協力体制を整えておくことの大切さ
可能であれば、治療当日はパートナーやご家族に付き添ってもらい、待合室で赤ちゃんを見ていてもらうのが最も理想的です。お母様が一人で赤ちゃんの面倒を見ながら治療を受けるのは、心身ともに大きな負担となり、治療に集中できない可能性もあります。
付き添いが難しい場合でも、治療の時間だけでもご自宅で赤ちゃんを見てもらえるよう、事前に協力をお願いしておきましょう。ご自身の治療に専念できる環境を整えることは、安全で質の高い治療を受けるために非常に大切です。周りのサポートを上手に活用することも、育児期を乗り切るための知恵の一つです。
意外と重要?治療当日の服装と持ち物リスト
治療当日の服装は、リラックスできる楽なものがおすすめです。特に、上下が分かれているパンツスタイルの方が、診療台での体の動きが楽になります。
また、急な授乳に対応できるよう、授乳しやすい服装を選んでおくと安心です。持ち物としては、ご自身の保険証や診察券に加え、赤ちゃん用の「お出かけセット」を万全に準備しておきましょう(おむつ、おしりふき、着替え、ミルク、お気に入りのおもちゃ等)。
また、歯科医師に聞きたいことを忘れないよう、質問リストをメモに書いて持参するのも良い方法です。事前の準備が、当日の心の余裕に繋がります。
授乳中の歯科治療、麻酔以外の薬は大丈夫?
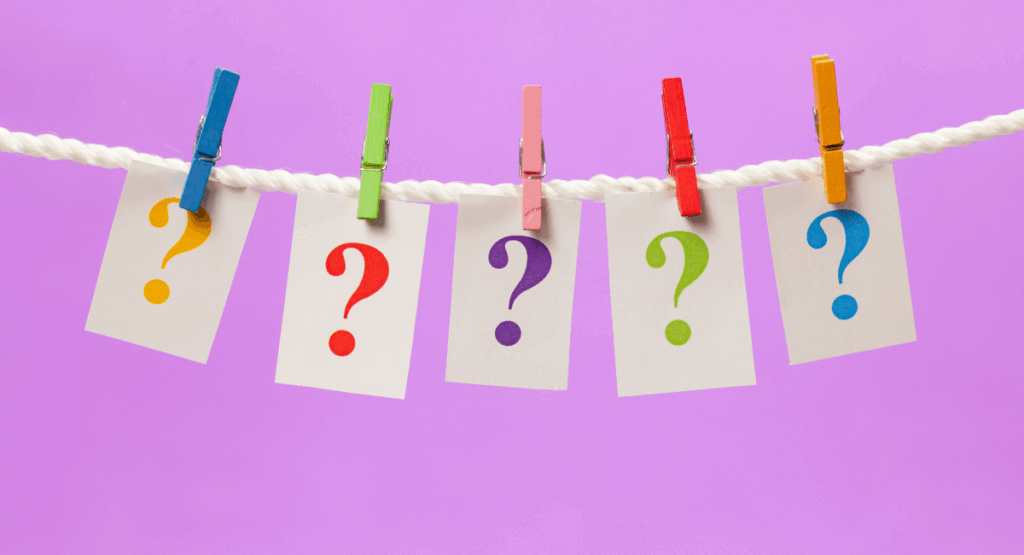
痛み止め(鎮痛薬)の選び方
抜歯後など、歯科治療の内容によっては、麻酔が切れた後の痛みを和らげるために痛み止め(鎮痛薬)が処方されることがあります。授乳中のお母様に処方する場合、歯科医師は母乳への影響が最も少ないとされる薬剤を選択します。
その代表格が「アセトアミノフェン」です。アセトアミノフェンは、多くの小児用解熱鎮痛剤にも使用されている成分であり、授乳中でも安全に使用できる薬剤として広く認識されています。
市販の痛み止めの中には、授乳期間中は服用を避けるべき成分が含まれているものもありますので、自己判断での服用は絶対に避けてください。必ず、歯科医師から処方された薬剤を、用法・用量を守って正しく服用することが大切です。
抗生物質が必要になった場合の注意点
歯ぐきの炎症が強い場合や、細菌感染を起こしている場合には、感染を抑えるために抗生物質(化膿止め)が必要になることがあります。抗生物質と聞くと、赤ちゃんへの影響を心配されるかもしれませんが、授乳中でも安全に使用できる種類は数多く存在します。
歯科では、主にペニシリン系やセフェム系といった、赤ちゃんへの影響が少ないことが確認されている抗生物質を選択して処方します。お母様の感染症をしっかりと治療することは、結果的に赤ちゃんの健康を守ることにも繋がります。
処方された際は、症状が改善しても途中で服用をやめず、必ず指示された期間、最後まで飲み切ることが重要です。
レントゲン撮影の安全性について
正確な診断のために、レントゲン(X線)撮影が必要になることがあります。放射線と聞くと不安に思われるかもしれませんが、歯科治療で用いるレントゲンは、撮影部位がお口周りに限定され、放射線量も極めて微量です。
これは、私たちが日常生活で自然界から浴びている自然放射線量と比較しても、ごくわずかな量に過ぎません。
また、撮影時には必ず放射線から体を守るための防護用の鉛エプロンを着用していただきますので、腹部や胸部(乳腺)への影響はまずありません。放射線が体や母乳の中に残ることも一切ありませんので、レントゲン撮影が授乳に影響を及ぼす心配はないと言えます。
気になる疑問を網羅!授乳と歯科治療のQ&A

Q. 麻酔後、どのくらい時間を空ければ授乳できますか?
A. 結論から申し上げますと、歯科の局所麻酔後、時間を空けずにいつも通り授乳していただいて問題ありません。麻酔薬が母乳へ移行する量は赤ちゃんに影響を及ぼさないほどごく微量であり、各種専門機関も授乳の中断は不要との見解で一致しています。
しかし、どうしてもご心配な場合は、麻酔薬の血中濃度が最も高くなる治療後1〜2時間を避け、次の授乳タイミングを3〜4時間後にしていただくと、より一層ご安心いただけるかと思います。
これはあくまで安心感を高めるための目安であり、医学的な必須事項ではありません。
Q. 治療後に搾乳(さくにゅう)する必要はありますか?
A. いいえ、治療後にわざわざ搾乳をして母乳を捨てる(破棄する)必要は一切ありません。かつてはそのような指導がされることもありましたが、現在の医学的・薬理学的な知見に基づけば、これは不要な対応です。
授乳中の歯医者で用いる麻酔は、母乳への移行量が極めて少なく、赤ちゃんへの影響は無視できるレベルであることが明らかになっています。
むしろ、搾乳をすることで、お母様の身体的なご負担になったり、母乳の分泌リズムを乱してしまったりする可能性も考えられます。どうぞ安心して、普段通りの授乳を続けてください。
Q. 2種類の麻酔薬を使った場合でも安全ですか?
A. 歯科で通常使用する麻酔薬は、「リドカイン」という麻酔成分と、血管を一時的に細くして麻酔を効きやすくする成分(エピネフリン)が少しだけ加えられています。
これを「2種類」と誤解されることがあるかもしれませんが、この組み合わせは治療効果と安全性を高めるための標準的なものです。血管収縮薬が麻酔薬を治療部位に留め、全身への拡散を抑えることで、結果的に母乳への移行量を減らすという、授乳中のお母様にとって有益な効果をもたらします。
歯科医師がこの標準的な麻酔薬を使用する限り、安全性に問題はありませんのでご安心ください。
Q. 無痛分娩で使った麻酔と、歯医者の麻酔は違いますか?
A. はい、全く異なる種類の麻酔です。無痛分娩などで用いられるのは「硬膜外麻酔」といい、背骨の近くにカテーテルを留置して下半身全体の痛みを広範囲に取る「区域麻酔」の一種です。
一方、歯科治療で用いるのは、治療する歯の周りの神経だけを狙って麻痺させる「局所麻酔」です。作用する範囲、使用する薬剤の量、投与方法、すべてが異なります。
歯科の局所麻酔は、体への影響が非常に限定的であるため、その安全性は極めて高く、日帰りで処置が可能なのです。同じ「麻酔」という言葉でも、その中身は全く違うものとご理解ください。
歯科医師からのメッセージ:お母さん自身のお体も大切に

痛みのストレスは母乳に影響することも
歯の痛みを我慢することは、想像以上に心と体にとって大きなストレスとなります。そして、この強いストレスは、お母様のホルモンバランスに影響を及ぼし、母乳の分泌を司る「オキシトシン」というホルモンの働きを抑制してしまうことがあります。
その結果、一時的に母乳の出が悪くなったように感じられることもあるのです。痛みの原因を治療し、ストレスから解放されることは、お母様ご自身の快適さのためだけでなく、円滑な授乳を続けるためにも繋がっています。
安心して治療を受け、心穏やかな毎日を取り戻しましょう。
ママの笑顔が、赤ちゃんの元気の源です
赤ちゃんは、お母様の表情や声のトーンから、その感情を敏感に感じ取っています。お母様が歯の痛みに顔をしかめ、つらい気持ちでいると、その不安は赤ちゃんにも伝わってしまうかもしれません。
逆にお母様が心からリラックスし、にこやかに微笑みかけてくれる時間は、赤ちゃんにとって何にも代えがたい安心感と喜びをもたらします。
ご自身の歯の健康を取り戻し、痛みのない快適な生活を送ることは、母子の素晴らしいコミュニケーションの時間を育むための大切な投資です。お母様の笑顔が、赤ちゃんの健やかな心の成長を支えるのです。
私たちは、お母さんと赤ちゃんの健康を全力でサポートします
「授乳中に歯医者に行っても大丈夫だろうか」「麻酔は本当に安全なのだろうか」。私たちは、お母様方が抱えるこうした特別な不安や疑問を深く理解しています。
だからこそ、科学的根拠に基づいた正確な情報を提供し、安全性が確立された方法で、お一人おひとりに合わせた丁寧な治療を行うことをお約束します。お母様ご自身が健康でいることが、ご家族全体の幸せに繋がります。
どうぞ、一人で悩まず、私たち専門家を頼ってください。あなたと、あなたの大切な赤ちゃんのために、私たちが全力でサポートいたします。
監修:愛育クリニック麻布歯科ユニット
所在地〒:東京都港区南麻布5丁目6-8 総合母子保健センター愛育クリニック
電話番号☎:03-3473-8243
*監修者
愛育クリニック麻布歯科ユニット
ドクター 安達 英一
*出身大学
日本大学歯学部
*経歴
・日本大学歯学部付属歯科病院 勤務
・東京都式根島歯科診療所 勤務
・長崎県澤本歯科医院 勤務
・医療法人社団東杏会丸ビル歯科 勤務
・愛育クリニック麻布歯科ユニット 開設
・愛育幼稚園 校医
・愛育養護学校 校医
・青山一丁目麻布歯科 開設
・区立西麻布保育園 園医
*所属
・日本歯科医師会
・東京都歯科医師会
・東京都港区麻布赤坂歯科医師会
・日本歯周病学会
・日本小児歯科学会
・日本歯科審美学会
・日本口腔インプラント学会
カテゴリー:コラム 投稿日:2025年8月26日

